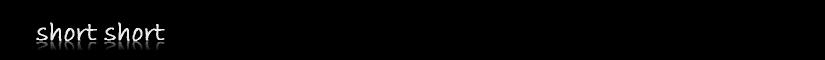おやつの時間
おやつの時間
ジェリーロラムが宿舎を訪ねて来たのは昼の鍛錬が終了した頃だった。
事務系の決済が必要な書類を持って来たのだと言う。
「久しいですね、ジェリー。着替えてきますので少し待っていてください」
ひょいと顔をのぞかせたギルバートがにこやかに言う。
汗まみれの上着は全て取り払われて、逞しい胸が晒されている。
「あ・・・はい」
目のやり場に困りながらもジェリーロラムが微笑むと、
ギルバートは鍛錬の疲れなど一切見せず軽い足取りで奥へと消えていった。
直後、洗い場の方からタントミールの声が響いてきた。
「隊長!仮にも総務の方の前で裸になるとはどういうことですか!
ああもう、服は全部洗濯しました!こまめに持ってきてくださいと
あれほど言っているじゃないですか!もう、これでも着ておいてください」
相変わらず女性は強いわねと楽しげに聞いていたジェリーロラムのところに、
着替え終わった隊員たちが集まり始めた。
ギルバートが就任してから半年間だけ乗船していたジェリーロラムとは
ほとんどのメンバーが顔見知りだった。
船を下りても何度か顔をのぞかせているので、後から入った面々も顔は知っている。
「ほらほら、パンケーキを焼いたからみんな座った座った。
ジェミマ、こないだ作ったジャムを持ってきておくれ」
ジェニエニドッツが、白い大きな皿にパンケーキを山と積んで運んでくると
隊員たちは目を輝かせて言われたとおり席に着き始めた。
普段穏やかなギルバートだが、鍛錬の時は容赦なく隊員たちをしごくのだ。
密度の濃い鍛錬をした後、夕飯までは隊員らの腹が持たない。
そこで、ジェニエニドッツはいつもこうしてお菓子を作って振るまうようになった。
「おいしそうね」
「ええ、もちろんよ。手作りのジャムもとてもおいしいのよ」
ジェリーロラムの隣に座ったヴィクトリアが嬉しそうに言った。
「いいわね、ジェニさんのおやつが食べられるなんて」
「特権ですよ」
向かいに座ったカッサンドラに向けたジェリーロラムの言葉は、
思いがけずやってきたギルバートに拾われた。
「先ほどはどうもスミマセン」
「いいえ、最近あんな風に上を脱いでいる方が周りにいないので」
「そうですね。さすがに総務の方はみんなきっちりと服を着ておられますから」
久しぶりに会うジェリーロラムとギルバートが談笑している間に
パンケーキと、白い皿、ジャムの入れ物、温かな紅茶が準備されてゆく。
「あら?マキャは?」
準備を手伝っていたジェミマがふと手を止めて辺りを見回す。
いつものっそりと座っている男の姿が見えない。
「まだ寝てるんじゃないか?今朝がたまで学生の海上訓練に付き合ってたからな」
マキャヴィティと相部屋のタンブルブルータスが眉ひとつ動かさずに言った。
「そろそろ起こしてあげた方がいいわ。夜眠れなくなるもの」
そう言って立ち上がったのはタントミール。
しかし、そこで彼女は固まった。
「やあ、ジェリーじゃないか。久しいな」
うっそりと部屋の入口に立っていた男が、うっそりと口をきいた。
寝起きだからかやや眠そうにしている。
しかし、この男の場合、常に眠たそうでもあるので本当のところはわからない。
「お、お久しぶりね。マキャ」
戸惑うように微笑んだジェリーロラムの目には、
ギルバートよりもなお一層厚くがっしりした立派な胸が映っている。
「マキャ!また裸で寝たの?ちゃんと着なさいって何度も言ったじゃないの!」
隊員たちの体調管理が仕事のタントミールは青筋を立てんばかりだが、
マキャヴィティは小さく首を傾げた。
「下は穿いてる」
「当たり前!とにかく、服を着ないならそっから先は立ち入り禁止だからね」
食堂への立ち入りを拒まれたマキャヴィティは、困ったように眉を寄せた。
「海上実習だったから全部まとめて洗ってしまったんだ。
ランパス、貸してくれないか?」
「生憎だな、俺もこれ以外は全部洗っている。コリコはあるだろう?」
「やだ。マキャが着たら破れるじゃん」
ランパスキャットとコリコパットがダメとなれば、
今度はマキャヴィティの目が入り口近くに居たカーバケッティに向いた。
「カーバ、余ってないか?」
「俺のは隊長が着てる」
本を読んでいるカーバケッティが目も上げずに言う。
それを聞いたジェリーロラムは思わずギルバートの方を見た。
「あ、カーバケッティになってる」
隊員たちのシャツは胸元に海軍のマークと名前が刺繍されているのだ。
海軍の司令部に併設される形でそれなりに広い刺繍工場があって、
そこで一枚一枚手縫いされるのだ。
そこで働くのは怪我で戦線に復帰できなくなった元海軍隊員や
近くに住んでいる一般の国民たちだ。
一つの雇用創出らしい。
「ちょっと大きいんですよね」
タントミールが渡したようだが、シャツに着られている感は否めない。
「マキャ、俺のがある。部屋にあるから着てこい」
やはり表情一つ変えず、タンブルブルータスが言う。
「そうか、すまんな。借りるぞ」
無事に服が見つかったマキャヴィティの足音が遠ざかってゆく。
すぐに服が足りなくなるのは男性隊員の常のようだ。
ジェリーロラムはギルバートに向き直った。
「シャツの支給を増やすように申請しておきますね」
「それは助かります!」
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
皆が揃った食堂でパンケーキを齧りながら、ジェリーロラムは
カッサンドラやヴィクトリアと近況を報告し合っていた。
通路を挟んだ隣のテーブルでパンケーキにジャムを塗りながら、
ボンバルリーナはその様子を見るともなしに見ていた。
「ジェリーって可愛いわよね。お菓子みたいじゃない?」
「そうね、あの笑顔だと男はたまんないでしょうね。
このジャムみたいに甘くって綺麗なお菓子ね」
相槌を打ったのはボンバルリーナの隣にいるディミータ。
カジイチゴのジャムが気に入ったらしく、その入れ物によく手が伸びている。
「ああいう可愛さって身につけようと思って身に付くものじゃないわ。
天性のものね。隊長だって結構ジェリーの方ちらちら見てるし。
ねえ、貴方たちもそう思うでしょう?」
ボンバルリーナは、目の前で黙々とパンケーキを口に運んでいるランパスキャットと、
次はどの味にしようか吟味するのに忙しそうなコリコパットに声を掛けた。
すると、ランパスキャットは口の中に残っていたものをごくりと飲み込んで
しげしげとジェリーロラムの横顔を見つめた。
そして、正面に座っているディミータの方を見た。
「俺はディミータの方が可愛いと思うが」
おもむろに口を開いてそんなことを言った。
隣のコリコパットが盛大に噎せている。
「そ、そんな、そんなこと言ったって、わた、私はちっとも嬉しくないんだから!」
真っ赤になったディミータが声を上げる。
ものすごく嬉しいんじゃないかとボンバルリーナは思っているのだが、
それを指摘すると色々ややこしくなりそうなので口を噤むことにした。
「どうしたのかしら」
突然のディミータの大きな声に驚いたジェリーロラムに、
いつものことよとカッサンドラが微笑みながら言った。
「仲がいいのね。彼らだけじゃなくて、この船はみんな仲が良くていいわ」
「そうですか。あれだけしごいていたらいつか嫌われるかもしれませんが」
厳しい鍛錬を課しているというのはギルバートにも自覚があったらしい。
ジェリーロラムはくすくすと笑った。
「隊長は優しい顔してものすごくシビアな要求をしてくるって噂があるんです。
どうやら本当のようですね」
「でも、戦って手柄を立ててほしいとかそういうのじゃないんですよ。
最悪の場合、自分で自分を守れる程度にはなってほしいだけですから。
この部隊には相変わらず戦闘専門の兵はいませんし」
「優しい顔して、鬼教官で、鬼の根っこはやっぱりすごく優しいのですね。
きっとこの部隊の皆さんはそんな隊長のことが大好きなんでしょうね」
照れたように俯いたギルバートは、頬を掻きながら躊躇いがちに上目遣いで
ジェリーロラムの愛らしい笑顔に視線を向けた。
「あの」
「どうかしましたか?」
「ジェリーは、どうなんです?」
カッサンドラが驚いたようにギルバートを見ている。
ジェリーロラムは訊かれたことの意味がわからずにきょとんとしていた。
「どうって、何がどうなのでしょう?」
「だから、ジェリーも元は僕らと一緒に船にいたわけですし、
その、貴女も僕のことを大好きでいてくれるのかってことです」
そこまで言って、さすがにいたたまれなくなったのか、
ギルバートは慌ててパンケーキに齧りついた。
その様子を唖然として眺めていたジェリーロラムは、
何だかおかしくなって肩を震わせて笑い始めた。
「すみません、隊長。なんだか貴方が無性に可愛らしく見えてしまって。
ええ、勿論ですよギルバート隊長。私も貴方のこと大好きです」
「そ、そうですか。それはよかった」
嬉しいのに何だか複雑な気持ちになったギルバートは、
そのまま黙々とパンケーキを齧り続けた。
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
「それでは、これで失礼いたします。ご馳走様でした」
「また来てくださいね」
ギルバートらが揃って敬礼でジェリーロラムを見送る。
同じように敬礼を返し、ジェリーロラムは仕事場に戻ってゆく。
「ほんと、変わった部隊ね。あの隊長の影響かしら、ね」
くるくると変わるギルバートの表情を思い浮かべながら
ジェリーロラムは次にあの部隊を訪ねる口実を考え始めた。
本編終了後の話。マキャが講師してる下りがあるので。
たった一つできること
たった一つできること
船影が見えた。
甲板に立っていたタンブルブルータスの声が船に響き渡る。
部屋にいたギルバートは具足を付けて甲板に上がった。
「相手の数は?味方ではないのですね?」
「残念ながら海賊のようです。船は小振りで五隻ほどでしょう」
「目を付けられましたね。もうすぐで着くというのに」
激務続きの第五艦艇部隊の業務代行で、
ギルバートたちは兵站部隊を率いて戦場に向かっている。
輸送船には勿論、大量の食糧や真水、武器、資材が積まれている。
喫水線の位置からも、相当の積載量が見て取れる。
「ヴィクトリア、いますか?」
「はい、ここに」
具足をつけたヴィクトリアがさっとギルバートの背後に立った。
「護送隊に伝達。半数を残し海賊を足止めする、残りは任務を継続。
防戦の全権は指揮官に与える」
「畏まりました」
ヴィクトリアは短く敬礼をして走ってゆく。
それを見送ったコリコパットが複雑な表情でギルバートに並び立った。
「半分だけで大丈夫なのですか?」
「僕らの任務は物資の輸送です。
戦局は険しい、この物資が届かなければ味方はかなり辛くなります」
「それはそうですが」
輸送部隊には護送部隊が付けられる。
海賊などに狙われやすい輸送船を護衛するのが主な任務で、第四艦艇部隊がこれにあたる。
「コリコ、実際に血を流して戦っていない僕らができるのは食糧を届けることだけなんです。
それだけしかできなくても、それを待っている味方がいるから早く行かなければなりません」
「隊長はいつだって冷静ですね」
「信頼できる仲間がいますからね」
ギルバートは近づいてくる船影に背を向けて僅かに笑みを浮かべた。
そこにランパスキャットが走り寄ってくる。
真剣な表情でギルバートに耳打ちをしてすぐに走り去っていった。
「ランパスは素晴らしい指揮官です、戦局眼は僕の及ぶところではありません。
任せておけば大丈夫です」
「…心配なくせに」
「コリコ、あなたは僕のことを知りすぎていますね。でも、結果は心配していません。
あの第四部隊員たちもランパスとタンブルが訓練していますからね、よく統制が取れています」
伝令と指示が船を駆け抜ける中、ギルバートはふいにコリコパットに目を向けた。
「僕らを信じて待つ味方と僕が信じる隊員たちがいるから僕はこの道を選ぶことができます。
もしも、あなたが僕の位置に立ったなら違う道を選ぶのでしょうね」
「俺はそんな器じゃないですよ。隊長の判断はきっと最善なんです」
「それはコリコが僕を信頼してくれているからそう思うんですよ」
緊張の高まる船の上でギルバートは穏やかに微笑んだ。
「今はありがとうと言っておきましょう」
ランパスキャットの号令が響いて護衛部隊が一斉に転回する。
それを聞き届けてギルバートも声を張り上げた。
「帆を揚げろ!全速力でこの場を離れる!」
自分に何ができるんだろう、と問う。
あの3.11の後、きっとたくさんの人がそう自分に問いかけて、
その答えは見つかったのでしょうか。
祈りの歌を
祈りの歌を
「失われたモノはよみがえらない」
激しい戦闘が嘘のように静まりかえった船の上でマキャヴィティはぽつりと呟いた。
呆然としていたシラバブは、はっとして顔を上げた。
「俺はもっとずっと残酷で無慈悲な戦いをいくつも見てきた。
戦でなくとも、とんでもない嵐で船が木っ端みじんになる様も見た」
散らかった物は既に片付けられ、怪我をした隊員たちは
船室に運び込まれて手当を受けている。
「バブは大きい戦は初めてか?」
「・・・はい」
「そうか。戦は嫌いか?」
「・・・はい」
軍に入った上は戦も当然とシラバブは考えていた。
それでも、実際に起こった戦闘は想像以上に心身に堪えた。
「この部隊に入る前、俺は戦闘部隊にいてな。
あまりに多くを失った。上官も、友も、部下も」
「辛くないはず、ないですよね」
「何か一つ失うたびに胸が抉られるようだった。慣れはしない」
シラバブは僅かに震えている自分の手を見つめた。
隊長の厳しい訓練で険を握る手は何度も皮が捲れて硬くなっている。
それでも、その隊長や目の前のマキャヴィティに比べれば柔なものだ。
「私はまだ誰かを切ったりできないかもしれません。
怖くて、今でもまだ手が震えているくらいなんです」
「それでいい。命の奪い合いは怖がるくらいでいいんだ。
俺は喪失の痛みを嫌と言うほど知っていながら、
この手で知らない誰かに喪失の痛みを味わわせている」
マキャヴィティは強かった。
隊長のギルバートや副隊長のタンブルブルータス、ランパスキャットも然り。
あっという間に敵対する相手を蹴散らしていく姿は頼もしい限りだったが、
血塗れで戻ってくる彼らの表情は一様に強ばっていた。
そこに誇らしさなどまるでなかったことにシラバブは驚いたのだった。
「哀しんでいますか?」
「いいや、哀しんではいない。俺は守るべき者を守った。
もう、俺が倒した相手の痛みを思いやることはできなくなっているんだ」
寂しげな表情を浮かべるマキャヴィティの心境を見定めることはできず、
シラバブは束の間黙り込んだ。
「なあ、バブ。戦闘部隊にいた頃、俺は上陸作戦に加わったこともある。
戦闘の起きた街は悲惨だった。焦土になって煙が燻る街は酷かった。
いろんな物が焼けた匂いがするんだ。家も、生き物もな」
「・・・関係のない、そこに暮らしていた方々が巻き込まれたのですか?」
「許されるかどうかの問題でなく、古今東西戦ってのはそういうものなんだろう。
倒すべき物だけを倒せる軍や武器なんて存在しない」
シラバブが座っている木箱の隣にある樽に腰を掛けながら
マキャヴィティは暗い笑みを浮かべた。
「軍は軍の仕事をしている。それが罪だと言う者も確かにいるだろう。
だが、俺にとってそういった善悪の議論なんてのはどうでもいい。
俺は失いたくないから戦っている、今はただそれだけだ」
「マキャヴィティさんが失いたくないものは何です?」
「帰る場所だ。そしてそこで迎えてくれる者たち。
そうだな、具体的にはこの船にいるバブたちや俺の故郷のばあちゃんたち」
マキャヴィティに両親はいないとシラバブは聞いたことがあった。
彼を育てたのは木こりの祖父母で、信じられないくらい山奥に家があるという。
「ばあちゃんもじいちゃんも、近所のみんなも俺とは全然顔立ちや体格が違う。
少数部族なんだろうさ。俺は拾われたのかもしれん、聞いたことはないが。
でも、血は繋がっていなくても彼らはみんな俺の味方で俺の家族だから」
「国を守ることが生まれ故郷の皆さんを守ることに繋がるのですね」
「俺は単純だからそう思ったし、今のところ特に間違ってはいない。
タンブルやランパスは一度帰る場所すら失っている。
あいつらも二度とここを失いたくないだろうさ。だから戦う」
だから、とマキャヴィティはシラバブの方に目を向けて微笑んだ。
「守られることを負い目に感じる必要はない。
俺たちは戦うのが義務だが仲間を守るのは自分の都合なんだ」
「ありがとうございます」
「礼を言われるのも不思議な気分だな。ああそうだ」
樽に深く腰を掛けたマキャヴィティは、船室の壁に背を預けて目を閉じた。
「一つ頼みがあるんだが」
「何です?」
「歌って欲しいんだ」
シラバブは驚いたようにマキャヴィティの方を見たが、
彼は静かに目を閉じたまま微動だにしない。
とても歌を歌うような気分ではなかったけれど、
シラバブは少し考えてから透き通った声で言葉を紡ぎ始めた。
遠い昔、お母さんが歌ってくれた歌。
どんなに嫌なことがあっても、この歌を聞くと気持ちが鎮まっていった。
「良い歌だな。温かい詩だ」
呟いたマキャヴィティの頬が濡れていた。
空を見上げて、シラバブは歌い続けた。
彷徨う魂も、傷ついた心も、痛む身体も、今一時苦しみを忘れて安らげますように。
祈りの歌声は、静かな海に吸い込まれてゆく。
震災後第一弾だった気がする。
で、この後微妙に続いていたりするんです。
そんなわけで、祈りシリーズ第一弾。
手を差し伸べていいですか
手を差し伸べていいですか
小さな灯りをともした船室にはギルバートとボンバルリーナがいた。
その部屋の扉が三度ノックされた音でボンバルリーナは海図から目を上げ、
隣のギルバートを伺うように見た。
頭部に白い包帯を巻いた隊長は、振り返って扉に目を向ける。
「タンブルですか?」
「はい、少し話があるのですが」
「どうぞ、入って下さい」
ギルバートの言葉が終わるか終わらないかのうちに扉が開く。
長身痩躯の副隊長は敬礼をして部屋に入ってきた。
少し足を引き摺っている。
「タンブル、怪我は大丈夫なの?」
「手当もしてもらったし、元々大した傷でもないから大丈夫だ」
「貴方も隊長も大丈夫ばかり言うのね」
ボンバルリーナは苦笑してタンブルブルータスに椅子を勧めた。
日没まで続いた戦闘は優勢で終わったが、
率いている戦闘員たちには負傷者も多く楽な戦ではなかった。
「僕らは少々怪我したって平気なんですけどね。
周りの貴女たちには心配を掛けて申し訳ないと思っていますよ」
中央特殊部隊の任務の一環で戦場に援軍として赴くのは初めてではない。
しかし、ここまで激しい戦になったのは今回が初めてだった。
戦場を見渡して指揮を執るタイプではないギルバートも、
戦闘員を率いていたタンブルブルータスも戻ってきたら傷だらけで、
勿論彼ら以外の戦に出ていた海軍兵たちはみなどこかしら傷を作っていた。
「それで、タンブルはどうしたんです?話があるとか」
「まあ、そうですね。この部隊の撤収についてなのですが」
「ああ、それなら今ボンバルと話していたところです。
負傷兵が多いので一端近くの港に寄ろうと思って航路を探していたんです」
別の援軍部隊が今夜中に到着する予定になっている。
ギルバートたちは負傷兵を纏めて中央に帰港する段取りになっていた。
「帰るのを、少し遅らせられませんか?」
「理由があれ遅らせますが、何か貨物に不備でもありましたか」
「そうではなく」
タンブルブルータスが躊躇いがちに言い淀んでいると、
ぱたぱたと駆けてきたらしい足音が扉の前で止まった。
「隊長!緊急事態です!」
「どうぞ、入って下さい」
勢いよく扉が開かれ、そこに立っていたジェミマがぴっと敬礼をした。
「どうしました?」
「海が燃えています。第8部隊の船が一艘、火が回って手が付けられません」
「隊員たちは?」
問いかけながらギルバートは部屋から走り出していた。
全員他の船に移動しました、と同じように走りながらジェミマが答える。
「夜襲ではないようです。昼間の戦いで流れた油に火が付いたんでしょう」
甲板に飛び出したギルバートに告げたのは、
赤く燃える船を難しい顔で見ていたランパスキャット。
「ここから離れた方がいいですね。
ランパス、マキャに言っていつでも出帆できるようにしておいて下さい。」
ランパスキャットは敬礼をして操舵室へと向かった。
入れ違いにタンブルブルータスがギルバートの隣に立った。
「すみませんタンブル、話の腰を折ってしまいましたね」
「いえ、緊急事態ですから」
赤々と燃える船は、遠からず崩れ落ちるのだろう。
目を細めて、海を這う炎を見つめていたタンブルブルータスは
軽く頭を振って炎に背を向け欄干にもたれるようにして空を仰いだ。
「タンブル?」
「隊長、やっぱり帰るのは少し待ってもらえるでしょうか」
黒いはずの空も海も、船を嘗める炎の所為で不必要に明るい。
その光景を、タンブルブルータスが最初に見たのは彼がまだ幼い頃だった。
「何かありましたか?」
「何かあったわけじゃないんです。ただ、したいことがあるんです」
かつて、タンブルブルータスの故郷を焼き尽くした戦火。
大切な者を、帰る場所を、思い出を奪っていった炎。
夜の闇を照らす忌々しく恐ろしい火の手。
「したいこと、とは?」
「・・・この戦、そこの港で営まれていた暮らしを破壊してしまいました。
たくさんの家が焼けて港も使い物にならなくなっているのでしょう。
俺はただ、逃げるしかない者たちを少しでも助けたい」
炎から逃げ惑い、家も家族も探せなかったかつての自分は
タンブルブルータスの中で未だに哀しみの澱となって凝っている。
「罪滅ぼし、ですか?僕らがやったことに対して貴方が罪を感じていると?」
「違います。俺はこの戦が壊したものや奪ったものを背負うほど立派ではない。
自分の中にある、無力だった自分に向き合いたいだけなんです」
「・・・僕らは、そこに住む者たちにとっては暮らしを破壊した憎むべき相手です。
それをわかっていても、貴方は手を差し伸べたいのですね?」
唐突に、がらがらと大きな音が響き渡った。
とうとう船が崩れ始めたのだ。
ここから先、ただの木屑になるまではそう時間はかからない。
「俺は街を戦に巻き込んだ陸軍兵に連れられて食事の貰えるところに行きました。
ただそこに縋るしか無くて、憎いとか怖いとかそんなことは考えませんでした。
そんな者たちがいるのなら、俺たちはそこに行くべきではないでしょうか」
「そうかもしれませんね」
崩れゆく船を眺めていたギルバートは、タンブルブルータスに目を向ける。
「では、副隊長。どれくらい滞在できそうか、食料や薬の在庫を報告して下さい。
タイムリミットはその在庫次第としましょう。
僕はほかの部隊に話を付けてきますので、よろしく頼みますよ」
隊長の決断の早さに呆気にとられていたタンブルブルータスは、
思い出したように直立して敬礼をした。
「では、早速確認して参ります」
足を引き摺りながら、タンブルブルータスは船室に姿を消した。
「貴方はいつも部下に甘いですね」
少し離れた場所に控えていた副官は、微苦笑を浮かべてギルバートの背後に立った。
「そうではないですよ、カッサ。タンブルの言っていることが正しいのか否か、
僕の経験からは答えが出せなかったので身をもって経験することにしたんです。
さて、僕もほかの隊長さんに話があるので付いてきて下さい」
「畏まりました」
ギルバートが他の船に渡ると言うと、船員が慌てて梯子を持ってくる。
それを待つ間、ギルバートは考え込むようにじっと一点を見つめている。
「隊長」
カッサンドラは思わず声を掛けた。
「何ですか?」
「ありがとうございます」
きょとんとするギルバートは随分幼く見える。
カッサンドラは小さく吹き出した。
「ありがとうございます、隊長。タンブルにこの機会を与えてくれて感謝します」
引き続き、祈りシリーズ第二弾。
タンブルにとっては、夜空を焦がす戦火はトラウマ。
霊送り
霊送り
真っ暗だった。
所々で火が焚かれているが、それ以外に灯りはなかった。
月も星も痛いほどに煌めいていたけれど、どこまでが地で空で海なのかわからない。
少し前、この港町は戦火で焼き尽くされてしまった。
大きな漁船や商船が付けられることもあって随分と栄えていたが、
ほんの数日の間に町は燃えて灰燼に帰した。
国境に近く、隣の国に不意を突かれて攻め込まれたこの町を
占領されないようにするのが精一杯だったのだとシャム国陸軍将校は言った。
隣国と海上で激戦を繰り広げていた海軍艦隊にギルバートたちも参加していて、
戦の後始末のためにこの町に寄港したのは町が焼けてから数日後のことだった。
「あの時は船を付けようにも、瓦礫が湾を埋めていてどうにもならなかったのに」
「そうですね。目を見張る復興ぶりです」
自分たちで調達してきた魚を火で炙りながら、ギルバートが呟いた言葉に
隣で魚に串を通していたカッサンドラが頷いた。
「町には多少なり焼け残った物があったのにな。きれいに片付けられている」
「正直片付けられていて良かったと思う。あれは悲惨だったからな」
「何が焼けてたのかわからないくらいに異臭と腐臭で気がおかしくなりそうだった」
マキャヴィティとタンブルブルータスは時々思い出したように薪を火にくべながら
ぽつぽつと言葉を交わし、そこにカーバケッティも混じる。
「涙が出てきたもんだ、自分でも気付かないうちに。
自分の家族が死んだわけでもないし、そもそもこの町に来たのも初めてだったのに」
「焼けたところから焼けた家族探すの手伝ってさ、怪我した町の衆の治療して
食料何とか調達して寝る場所こしらえて。俺たちはできる限りにことはしたつもりだ」
「それでいいんです」
ギルバートが魚をくるりと返しながら口を挟んだ。
「僕らはあの時頼まれてもいないのに勝手にここに来て勝手に手助けをしようとしたんです。
その時点で既に自己満足ですし、どこまで何をすれば良いかなんて答えはありません。
今回は視察と復興支援という任務ですが、それとて何をすれば良いか誰も教えてはくれませんし」
「町のみんなはけっこうあたしたちに好意的だと思うわ。
戦の後にあたしたちが食事配ったりしていたことを覚えていてくれた子どももいたし」
蒸し焼き用に大きな葉っぱに魚を乗せて、キノコや海藻と一緒にくるんでいたジェミマが言う。
そのキノコも町の衆が分けてくれた物だ。
「何の見返りも無いとわかっていながら皆さんが限界まで働くのを見ていて下さったのですね。
本当に、あの後は僕らも帰り着くまで何度気が遠くなったか」
「食料の在庫が危険な状態でしたね」
「タント、それを言うなら水の備蓄の方がもっと危険だったって」
これ以上は隊員の身体が危険だと、
タントミールとディミータがギルバートに引き上げの決断をさせた時点で
船の在庫は既に安全航行できる基準を大幅に下回っていたらしい。
「食事は一日一回で補給地まで五日間。たった五日だけど、
食料が大事なんだって身につまされたわ」
「そうよ、食事はエネルギーの源だもの。大切に決まっているわ。
獲った魚と海藻に焼け残った芋すりつぶして焼いただけの団子を町のみんなが喜んでくれて、
それだけだったけど自分は無力じゃないのかもしれないって思えたの」
ジェミマはそう言って、器用に棒を使って炎の下に空洞を作ると
葉にくるんだ魚をそこに押し込んだ。
「・・・自己満足だけどね」
「うん。私も、怪我の治療ができて良かったって自己満足してる」
タントミールはジェミマに借りた包丁で芋の皮を剥きながら呟くように言った。
地面の下に茎を成長させるこの芋だけは、戦の前も後も変わらず育っているという。
町の衆も、焼いたりすり潰したりして何かと重宝しているようだ。
「隊長」
不意に、黙々と魚を焼いていたボンバルリーナがギルバートに声を掛けた。
そのまま彼女の視線がふいと自分の後ろに滑ったのを見て取ってギルバートが振り返ると
酒壺を下げた町の頭が数名の町衆を従えて立っている。
「隊長さんよ、ちゃんと食ってるかい?」
「ありがとうございます、いただいています。このキノコ、おいしいですね」
「そうだろう?あっちの山の方は焼けなかったからな、キノコくらいしか採れねえけど」
町の頭の声は大きいが潮焼けして掠れている。
この町の男たちは漁をして暮らしていたのだから、頭のような声の者は多い。
「今日は特別だからな、酒でも飲んでくれよ。全然酔えねえ弱いやつだけどな。
あんたたちは偉そうにしねえし、目一杯手伝ってくれるからよ。
明日くれえは仕事しねえで子供らにかまってやってくれや、
あんたたちと遊びたくて仕方ねえってさ」
ギルバートは微苦笑を浮かべて任務の途中だからと酒を断ろうとしたが、
その前にコリコパットが立ち上がって敬礼をした。
「ありがとうございます。お心遣い感謝します」
「いいってことよ。この酒は山向こうの村の奴らがくれたんだ。
奴らも何かと気に掛けてくれてっからさ、せいぜい俺達も気張らねえとな。
後でみんな集めて霊送りやっからあんたたちも来てくれよな」
町の頭たちは酒壺を置いて立ち去った。
「コリコ、勝手なことをするのは」
「いいじゃないですか」
思いがけずギルバートの言葉を遮ったのはディミータだった。
「特別な日だと言っていたでしょう?
忙しくて忘れているかもしれませんが、今日は大つごもりです。
酒を飲む日というわけではありませんが、他に特別な夜に添える物もありませんから」
「なるほど、彼らの粋な計らいということですね。もう、大つごもりですか」
良い具合に焼き上がった魚を、串に刺したままディミータに渡して
ギルバートは考え込むようにじっと火を見つめる。
「あの、先ほどの方が"たまおくり"とおっしゃっていたのですが何をするのですか?」
「あたしは知らない。カーバ知ってる?」
シラバブからの質問をランペルティーザはそのままカーバケッティに投げた。
民俗学的分野には比類無き知識を持ち合わせる参謀官は、あっさりと頷いた。
「古くから伝わる鎮魂の儀式だな。旧い年と共に魂を神にお返しするのさ。
大抵は親族の間でその年に亡くなった者の供養として行うもんなんだけど」
戦でたくさんの命が失われたこの年は、町のみんなで霊送りをすることになったのだろう。
「私、霊送りの舞を知っているわ」
自分で焼いた魚を食べていたボンバルリーナが独り言のように呟いた。
「王宮では新年祭で霊送りをすると聞いたことがあるけれど、その時に?」
ヴィクトリアが訊ねると、ボンバルリーナはそうよと答える。
「昔は王宮で踊り子でね、私は舞に関してはそこそこ認められていたのよ」
「霊送りの舞は静かで厳かなものだと聞いたわ」
「その通りよ。厳粛な雰囲気で踊るからすごく緊張するし。
今はたぶん、身体が付いてこないと思う」
くすっと笑ったボンバルリーナは、突如がしっと手を掴まれて飛び上がらんばかりに驚いた。
更に彼女が驚いたのは、ギルバートの真剣な眼差しが正面にあったことだ。
「隊長?」
「新年祭で舞ったということは、新年慶祝の舞も知っていますね?」
「・・・知っていますが、何か?」
不審そうに眉を寄せるボンバルリーナのことは見えていないのか、
ギルバートは勢いよく立ち上がって隊員たちを見回した。
「町の霊送りが終わったら僕らは新年を祝うことにしましょう。
せっかく舞い手がいるのです。カーバも祝詞くらい知っているでしょう?」
「知ってはいますが俺は神官でも何でもないですよ」
「僕の故郷には神官などいませんでしたが、各家持ち回りでその年の祭主を務めていましたよ。
必要なのは神を慶ぶ想いであって肩書きではありません」
もっともらしく無茶を言うのはギルバートの十八番だと隊員たちはよくわかっているので、
無茶振りをされたカーバケッティですら言い返すことなく了承した。
ボンバルリーナは承知したなどと一言も言っていないのだけれど、
既にギルバートの中では了承済みになっているらしいとわかってか小さく溜め息を吐くだけだった。
「僕は部族の長となるべく育てられてきて、新年の儀式の執行も習いました。
新しい年を迎える儀式は故郷ではとても大切にされていたものです。
山奥から海を望み、龍神に向かってその年の加護を祈るのです」
「だったら、ボンバルの舞と隊長の祈念を両方やればいい」
杯に酒を注ぎながらランパスキャットが言うと、コリコパットも頷いてニッと笑う。
「隊長が祈ってくれればきっと海の神は聞いて下さる。
龍神は海の神、海で生きる俺達にきっとご加護がありますよ」
「そうですね、そうなるように祈りましょう」
すとんと座ったギルバートは、カッサンドラに差し出された杯を受け取った。
他の隊員たちは既に杯を手にしている。
「祈りましょう、ここで生きた霊たちが神のもとに帰って安らげることを。
そして、新しい年の龍神の加護が我等にあらんことを。では、乾杯!」
杯を掲げた隊員たちは、それぞれに杯を空けて久々に心からの笑みを浮かべた。
「おいしいですね。まだまだ頑張れそうな気がします」
シラバブが言うと、ランペルティーザとジェミマが大きく頷いた。
マキャヴィティとランパスキャットは早くも二杯目に手を伸ばしている。
カーバケッティとボンバルリーナは何やら打ち合わせを始め、
タンブルブルータスはちびちびと酒を飲みながら焼けた魚を頬張っている。
タントミールとヴィクトリアは切った芋を刺した串を火の周りに突き刺し、
コリコパットがそれにぱらぱらと塩を振っていく。
ヴィクトリアはボンバルリーナが剥きかけて放置した芋を手早く処理していた。
カッサンドラとディミータは仲間たちのそんな様子を眺めながらのんびりと酒を飲んでいる。
「みなさん、また暫くはよろしくお願いしますよ」
ギルバートが言うと、隊員たちは一斉に振り返り揃って敬礼をする。
炎にあかあかと照らされる隊員たちを見渡して、ギルバートもまた敬礼をした。
「中央部隊になって慣れない仕事も山のようにあると思います。
でも、魚を突く銛を鶴嘴に持ち替え、舵ではなく鋸を手にとって慣れない作業をしながら
懸命に立ち直ろうとしている町の皆さんを見ていると、絶対に弱音は吐きたくないと思えるんです」
ギルバートの視線の先で小さく頷いたのはタンブルブルータス。
戦火に巻き込まれたこの町に手を差し伸べたいと最初に言ったのは彼だった。
今回も、寡黙なこの男は朝から晩までずっと働いている。
「この町はきっと蘇ります、町のみんなの力で。
そのささやかな手助けができるならそれ以上は何も望みません」
「僕らは無力じゃないですよね、タンブル。僕らが町の皆さんに励まされているように、
きっと僕らの姿を見て頑張ろうと思ってくださる方々がいらっしゃるはずです」
刻々と更けてゆく夜。
この夜、魂たちは旅だってゆく。
残された者たちは、哀しみを抱きながらもすでに立ち上がっている。
「大丈夫。海の神はきっと、この町を見放しません」
ギルバートは胸元に煌めく龍の首飾りに触れて、祈るように呟いた。
祈りシリーズ第三弾・・・だっけ。
新年用に書いたものだけど、何か慶賀って感じじゃないなあ。
背負ったもの
背負った者
微かな喧噪
怒声 悲鳴 忙しい足音
光る刃 血走った目
驚愕 戦慄 恐怖
猛る炎 血飛沫
倒れゆく身体 奪われた命
燻る崩れた家 一面の血溜まり
鳴き声 呻き 虚ろな目
冷たくなった身体 開いたままの瞳孔
家族だったはずの、何か
たった一夜のこと。
失ったものはあまりに多く、もはや数えることはできない。
それでも、忘れたのでも忘れようとしたのでもないとランパスキャットは言った。
「失ったと自覚する前に地獄を見た。
失ったと自覚した頃には哀しむことができなくなっていた、それだけだ」
目の前に座っている小柄で小太りの訪問者を冷ややかに見下ろし、
嘲るような薄い笑みを口の端に浮かべたランパスキャットは
手の中で弄んでいた書簡を勢いよく破り捨てた。
「貴様・・・」
ここ最近、戦場での目覚ましい活躍で名も地位も上げているランパスキャットを、
血も涙もない指揮官と揶揄した訪問者は、参謀本部の中堅参謀官だった。
「名誉挽回のチャンスをやろうと言うのにとんだ態度だな」
「名誉挽回?意味がわからん」
「敵の捕虜にされた上、陸軍にも見捨てられたのだろう。
炎天下で働かされて、生体実験の実験台にされて、挙げ句手籠めにされたとか。
これが不名誉じゃなくて何だってんだ?」
苛立ちを隠さない参謀官の口から出てきた言葉で
ランパスキャットの表情は完全に消えて青ざめた。
その様子を見ていたタンブルブルータスは、ずっとランパスキャットの隣に座っていたが、
最初に名乗ってから今まで口を挟むことなく黙っていた。
「参謀官殿、暴言が過ぎます」
タンブルブルータスは漸く、静かに口を開いた。
「ランパスキャットも言いましたが、我々はこの要請を拒否します」
かねてよりシャム国の陸軍と敵対している国があって、
その戦に海軍も参戦してはどうかという声が上がっていた。
参謀本部は乗り気だが、総司令部がかなり渋っているという。
意義も見いだせなければ大義名分も無い、と総司令官のジョージなどは一蹴している。
そんな総司令部を説得したい参謀本部が担ごうとした候補に
ランパスキャットやタンブルブルータスの名が挙がっていた。
理由は単純で、かつて敵国との戦に巻き込まれて悲惨な目に遭っているのだから、
復讐心を抱くのは当然だろうというのだ。
「ランパスキャット少佐、相手は自分を虜にして虫けらのように扱ったのだぞ。
タンブルブルータス中尉も、奴らの所為で戦災孤児になったのではないのか。
何故戦おうとしない?雪辱のまたとない機会だぞ」
「参謀官殿、我々は復讐のためにここにいるわけではありません。
貴方は戦火に巻かれ、失ったものの多さに打ちのめされたことはないのでしょうね」
タンブルブルータスはじっと相手の目を見て坦々と喋る。
そこに静かな怒りと苛立ちがあることなど初対面の参謀官が気付くはずも無い。
「我々は戦火を持ち込んだ敵国に憎しみや復讐心を抱いてはいません。
ただ、自分で受け止めきれないほどの哀しみに絶望しているだけなのです」
「ふん、腰抜け共が」
舌打ちと共に参謀官が吐き捨てた瞬間、
鈍い打撃音と乾いた木の割れる音が部屋中に響いた。
「何と言われようと」
机に打ち付けた拳はそのままに、ランパスキャットは感情の失せた目を相手に向けた。
「俺も、タンブルも、勿論この部隊の他の皆も、
貴様らの都合で戦の宣伝と正当化に利用されるのは御免だ」
「この男の言うとおりです。無用な戦で疲弊するのは民と、そして国そのものです。
我々の過去をどんな美談に仕立てたいのかは知りませんが、
ねじ曲げて脚色された話を使って、民の戦への意識を鼓舞するなど下策でしょう」
タンブルブルータスからも冷ややかな声を浴びせられた参謀官は、
目を怒らせて小太りの身体を小さく震わせる。
「ならば、いつまで経っても汚名は濯げないぞ」
「さっきから汚名だの不名誉だのと、何を意味不明なことを言っているんだ?」
まるでわからないとでも言うかのように、ランパスキャットは僅かに首を傾げて続けた。
「俺は敵に捕らわれたことは否定しない。
だが、そこで味わった苦痛と陸軍から受けた裏切りは
痛む傷でこそあれ、不名誉なことだなどと思ったことはない」
「強情だな。屈辱だと素直に認めれば楽になれるものを」
「屈辱と汚名は関係ない。そもそも、あんたに俺の思いが何故決められる?
自分の過去は自分が知っている。己の過去を決められるのは己だけだ。
俺が汚名を被っているというのなら、その汚名を着せたのはあんたたちだ」
反駁は許さないと、酷薄な光を湛えた双眸が無言で圧力を掛ける。
興奮を一気に冷まされた参謀官は、逆に底冷えするような圧迫感に戦慄いた。
それを見て取ったタンブルブルータスは、立ち上がって扉を示した。
「お引き取り下さい、参謀官殿。これ以上の説得は双方にとって無意味です。
我々は既に戦の絶望を知っています。
戦に意義や大義を見いだせない限り、我々は協力できません」
せかされるようにして立ち上がった参謀官は腹の虫が治まらないようで、
見下ろすように立っているタンブルブルータスを睨み付けた。
「お前たち、この無礼は」
「無礼?我等には命令を拒否する権利はありませんが要請を拒否する権利はあります。
それを行使するためにただただ理由を述べたに過ぎません。
総司令部も我等が正論を言っていると認めてくれるはずです」
長身の副隊長は、かがむようにして強面を参謀官にぐいと近づけると、
その耳の傍で早く帰った方が身のためですよと囁いた。
「で、では失礼する」
殺伐とした空気を纏ってランパスキャットに睨まれていることに気付き、
参謀官は慌てて扉に向かって歩いて行った。
小太りの身体が視界から消えるまで待って、タンブルブルータスは振り返った。
「大丈夫か?ランパス」
「やっかみには慣れている。そのはずなのにな、いつもどこかが抉られるようだ」
痛いな、とランパスキャットは呟いた。
そうだな、とタンブルブルータスは頷く。
忘れられるはずがなかった。
深く強く刻みつけられた痛みを。
だからこそ、その痛みを誰かに押しつけるような道は選ばせるわけに行かないのだ。
本編終了からけっこう後の話。
ギルバートは一族を背負っていたけれど、
タンブルやランパスは重い過去を背負って生きてるんです。
前を向いて 希望となって
前を向いて 希望となって
荷物の詰まった麻袋を担ぎ上げてコリコパットは部屋を出た。
袋はぱんぱんに膨れているが、詰まっているのが服ばかりだからかさして重くもない。
「手伝おう」
コリコパットが階段を下りたところにランパスキャットが立っていた。
「いいよ、俺がやるから」
「まあそう言うな」
ランパスキャットは隊舎の入り口に積んである木箱をひょいと抱え上げると、
コリコパットに並んで歩き始めた。
向かう先は少し離れた場所にある別の隊舎だ。
空箱では無いかと思うくらい平然と木箱を運んでいるランパスキャットを
ちらりと横目で伺いながら、コリコパットは迷ったように口を開いた。
「俺がいなくなったらランパスは寂しかったりする?」
「何だよ急に」
「何となく訊いてみただけ」
コリコパットとランパスキャットは長い付き合いだ。
年若いコリコパットが初めて海に出たときから一緒に働き戦ってきた。
だから、この手の質問ははぐらかされるだろうとコリコパットはわかっている。
「痛いな」
「へ?何が?」
ゆえに、答えが返ってきたところで答えだと思えなかったのは仕方がない。
首を傾げたコリコパットをランパスキャットが睨む。
「お前、自分で質問しといて何がってのはどういう了見だ?」
「ああ、そっか。でも、痛いってどういうこと?
整備の仕事だったらランペルでもできるし、戦闘だって俺は得意じゃないし」
「そんなんじゃない」
ランパスキャットは前を見たままコリコパットの言葉を遮るように言った。
「コリコの整備技術は俺らも買ってるし、海の状態だって一番正確に見通せる。
だが、それはお前も言うようにランペルや隊長なんかでも代わりは務まる」
「だよな。隊長なんかジンギスの子孫だしな、潮の流れとか読むのすっげえうまいもん」
「そうだな」
頬を紅潮させてギルバートの凄いところを語るコリコパットの言葉をランパスキャットは苦笑混じりで聞く。
それでも、やはり一番正確に潮の流れを見極められるのはコリコパットなのだということは、
ギルバート部隊の全員が文句なく認めるところなのだ。
「・・・コリコ、お前は俺と初めて会ったときのことを覚えてるか」
「覚えてるぞ。満潮になったら沈むようなとこで寝てたから吃驚した」
「いや、ありゃあ寝てたんじゃなくて動けなかったんだって言わなかったか?」
そうだったかも、と言いながらコリコパットは麻袋を担ぎ直す。
ランパスキャットは相変わらず重さを感じさせることなく箱を抱えている。
「負け戦の遠征から戻ってすぐだったからな、あの時は本当に身体がぼろぼろだったんだ。
それなのに上の奴らがすぐにまた遠征の指令持って来やがったから思わず部屋から逃げたんだが」
「逃げたってどうしようもないし、逃げたってわかったら懲罰食らうのにな」
「そりゃまあ俺だってわかってたさ。でも、気付いたらあの場所にいた」
下手に動いたら見つかるかもしれないという思いと、
怪我で重い身体がランパスキャットを動けなくしていたのだ。
そこに来たのが、その頃はまだ孤児院で育てられていた少年時代のコリコパットだった。
その少年コリコパットはランパスキャットを孤児院まで連れて行って手当を受けさせ、
海軍の上官たちには自分が迷子になっているところを助けられたのだと無邪気に言った。
「あれでお咎めなしだったし、孤児院の院長さんが口添えしてくれたおかげで次の遠征は免れた。
俺はコリコにかなり感謝したんだぞ。伝わったかどうかは知らんが」
「たぶん伝わってたと思う。じゃなかったらその後友達になったりしないしさ」
「ふうん。お、あれか?」
向こうの方に小さく見えてきたいくつかの隊舎に目を凝らすランパスキャットに、
一番右端だよとコリコパットは言った。
「・・・なあ、コリコ。お前が思ってる以上に俺たちはお前に感謝してるんだぞ。
カーバも、カッサもな。もちろんギルバートも。
俺もあいつらも、独りで過去背負い込んで足掻いてたところをお前に引っ張り上げられた」
「そうなんだ?俺は全然そんなつもり無かったけど。
カーバは俺の話いっぱい聞いてくれたしランパスは甘えさせてくれたし、カッサは勉強も見てくれたな」
「カッサは妹や弟失っていたから、お前にその影を見てたと言えなくないだろうな。
カーバは独りで平気なふう装ってるけど、実際は強がってるだけで寂しかっただろうし。
あの嵐の時にカーバがお前を庇ったのもあいつが本気でコリコを守ろうとした証だろうな」
カーバケッティは、当時学生だったコリコパットに戦わせるわけにいかなかったからと言っている。
それも嘘ではないが、命を掛けて守るに値すると思わなければカーバケッティは見放していただろうと、
カーバケッティの冷徹な部分を知るランパスキャットやディミータは今でも思っている。
「カーバにとってギルバートの意志を貫かせること以上に大切なものはなかったはずだ。
でも、あいつは身体を張ってお前を守った。俺だってそうするかもな。お前は失えない」
「ちょっと大袈裟だと思う。それに、失えないって言うなら俺がいなくなったら寂しいだろ?」
「痛いと言った。コリコ、お前はみんなの希望にならなければいけない。
すごいプレッシャーだぞ、覚悟しろよ」
「何で俺なんだろう」
「戦場にいる者の命をつなぐ役割だ。
その役割の重さを知り、かつ遂行できると認められたってことだ」
小さく唸ってコリコパットはぴたりと脚を止めた。
先に行きかけてランパスキャットも立ち止まる。
「どうした?休憩か?」
「うん、ちょっと」
日々鍛錬している身にはこれしきの荷物運びくらい全く堪えないが、
コリコパットは袋を地面に置いた。
それを見てランパスキャットも抱えていた箱を下ろす。
「不安か?」
「それもあるかもしれないけど」
「寂しいか?」
「・・・ちょっと」
僅かに俯いたコリコパットの頭をくしゃりと撫でて、ランパスキャットは幽かに笑みを浮かべた。
「コリコ、お前は俺たちの中での案内人なんだ。俺もカーバも、ギルバートだって先が見えなくて迷子だった。
死を選ぶことはできないのにどうすべきか迷って下を向いて疲れ切って何とか生きてきた。
だからコリコが俺たちの傍からいなくなるのは怖い、痛いくらいに怖いと思う」
「ランパスたちが俺を必要としてくれたみたいに、戦場にいる海軍兵たちも俺が必要なのかな」
「当然だ。食料も武器も薬も包帯も、あって当たり前の物が無いと戦にならない。
希望になれよ、コリコ。そのために俺たちは痛みを甘受することにしたんだからな」
コリコパットはギルバート部隊を離れる。
海軍総司令部直々の要請で、
戦場に物資を届ける第五艦艇部隊を新規編成する際の隊長に抜擢されたのだ。
必要なのは戦いを指揮する力ではない。確実に戦場に物を届ける能力こそ必要だった。
「士官学校も出てないしこれと言った功績もないし、全然現実感ないんだけど」
「ジョージ総司令官は良く調べている、選ばれたからには胸を張って若い隊員たち率いて行けばいい。
ほら、行くぞ。まだまだ荷物あるんだからな」
「うん」
軽々と箱を持ち上げて歩き始めるランパスキャットを、コリコパットは麻袋を半ば引き摺るようにして追った。
「ランパスが隊長になればよかったのに」
「戦闘部隊の編成だったら声が掛かったかもしれんな。
まあ心配すんな、心強いパートナーがいるだろう」
「バブのこと?」
コリコパットが部隊を抜けると聞いたその場で、シラバブは自分も行くと言い出した。
周りにいた全員が驚いたが、
ギルバートとカッサンドラが総司令部に手回ししてめでたく同行することになったのだ。
特に奮闘したのがカッサンドラで、女性として何としてもシラバブを行かせてやりたかったという。
残念ながら、コリコパットは未だその意図を解せていないが。
「バブもそうだし、お前の親友の何とかってやつもいるんだろう?」
「パウンシヴァルだ。特殊工作員なんだけど・・・船で何するんだろう」
「諜報要員でも甲板仕事は一通りできるだろうが」
「そうだよな」
隊舎の前には運ばれてきた荷物が、屋内への搬入待ちで無造作に置かれている。
コリコパットとランパスキャットの姿を認めたのか、搬入作業中の若い隊員たちが直立で敬礼した。
「話には聞いていたが、本当に若い奴らばっかりだな」
「うん、俺より上ってほとんどいない」
「そうか。お前なら問題なく部隊率いていけるだろうよ」
「だといいけど」
部下になる隊員たちを見るコリコパットは、甘え上手な青年から若年の隊長の顔になっている。
その横顔を見たランパスキャットは、穏やかな微笑を浮かべた。
「コリコ」
「何?」
「何があっても、お前だけは前を向いて生きることを止めちゃいけない。
今までそうだったように、これからもそうあってほしいと俺たちは願っている」
「うん。俺、頑張れるよ」
みんながコリコパットを笑顔で送り出した。
コリコパットが必要とされていることをみんながわかっていたから、涙など見せずに祝福した。
これから彼が向かうのは厳しい戦場。
そこに至るまでにも数々の困難は付きまとう。
それでも行かなければならない。
希望となるために。
「あと、無事で帰ってこいよ」
「勿論」
コリコはあの後隊長に抜擢されました。
みんなの支えになってるんだとコリコ自身は気付かないけど、
みんなコリコのことが大好きなはず。