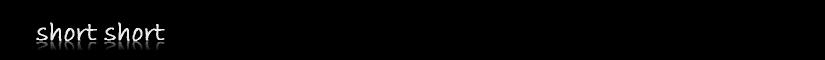錆びない覚悟
錆びない覚悟
陽気に鼻歌など歌いながら、赤毛の海賊は散らかった部屋を掃除していた。
つい先日の戦闘で骨にひびが入ったらしい左腕をつったまま
動く手と、時には脚なんかも使いながら器用に片付けている。
部屋と言っても、当然ながら船室のことで汚い上に臭いも酷い。
潮のにおいは勿論、酒や葉巻、汗の臭いやらなんやら
混じった上に暑さで発酵したのかすえた臭いはとんでもない。
とはいえ、何年も船上で暮らしているマンゴジェリーには
そんな悪臭など気にならなくなって久しい。
それでも掃除をしているのは、足の踏み場がないと嘆く
海賊らしくない真面目なバンダナ男の頼みを聞いてやったに過ぎない。
そのバンダナ男、マンカストラップは同じグロールタイガーの腹心で
マンゴジェリーよりも賊生活は長いというのに未だ健全な爽やかさを保っている。
ゴミと判断した者は迷わず捨てる。
それだけで随分すっきりするものだ。
床に散らばっている物はあるべき場所に戻して、ついでに床を拭けば
部屋は見違えるほどきれいになってしまった。
「マンゴ、お疲れ様。ちょっと休憩しない?」
片付いた部屋の真ん中で、マンゴジェリーが己の仕事に満足していたところに
ひょこっと顔を覗かせたのはスキンブルシャンクス。
これまた、海賊に似つかわしくない愛らしい笑顔の持ち主だ。
手には酒の壷と欠けた杯を二つ持っている。
「よう、スキンブル。船長のご機嫌はどうだ?」
「今日はすこぶる良いみたいだよ。おいしい酒が手に入ったんだ。
これ、一つかっぱらってきたから一緒にどうだい?」
「やるじゃねえか。入れよ、飲もうぜ」
部屋に踏み入れたスキンブルシャンクスは、ぐるりと視線を巡らせて
感心したようにすごいねと呟いた。
マンゴジェリーと向かい合うように床に腰を下ろしてから、
もう一度辺りを見回して微苦笑を浮かべる。
「この部屋、案外広かったんだね。キレイになるもんだなあ」
「だろ?これでマンカスの眉間の皺が減るんじゃね?」
「毛の抜ける本数も減るかも」
ふたりして、仲間を酒の肴に酒盛りが始まった。
スキンブルシャンクスがマンゴジェリーに杯を差し出し、そこに酒を注ぐ。
濃い山吹色をした液体から甘い匂いが漂う。
「何の酒?」
「果実酒だって。さっき寄った港の酒場にあってさ。
そこの親父が僕らの武勇伝を大層気に入ってくれてね。
一つ話すたびに酒の3壷くらいくれたんだ」
「そりゃあ気前の良い親父だな。毒でも入ってんじゃねえの?」
「あはは、天下のグロール一味に毒を盛る勇気がある奴はいないよ」
マンゴジェリーはお返しに、スキンブルシャンクスの杯に酒を注いだ。
互いに目の高さまで杯を掲げると、その後は一気に飲み干す。
「旨いな、思ったほど甘くねえし喉ごしが良い」
「清涼系の香草なんかも入ってるのかな」
杯を重ねてほどよく酒が回ってきたところで、スキンブルシャンクスは
マンゴジェリーの背後の棚に見慣れない小箱があるのに気がついた。
見慣れないというよりも、散らかり放題の部屋で目に付かなかっただけかもしれない。
「あれは何だろう?マンゴは知ってる?」
「どれだ?」
指し示された先を追ってマンゴジェリーは身体を捻った。
そこにはくすんだ鉛色の長方形の箱が納まっている。
「あの箱か?ありゃあ俺のだけど、見るか?」
「そうだね、見せてくれるなら」
スキンブルシャンクスが返事した時、既にマンゴジェリーの手は箱に伸びていた。
その手が無造作に箱を掴んでスキンブルシャンクスにそれを差し出す。
「案外重いね。君の私物はかなり珍しいと思うけど、大切なものなのかい?」
「大切ってのとはちょっと違うけど、捨てるようなもんでもないからな」
「ふうん。君は物に執着が無いからなあ。お宝にも興味無いみたいだし」
そう言いながら、スキンブルシャンクスは箱の蓋を取った。
雑に詰められた布とその上に置かれた探検が一本。
装飾もない。作りが良いわけでもない。そして。
「酷く錆びているね。使えないよ」
「もう使った後だ、そいつは血で錆びてんだ」
「ああ、そうか。これに何か思い入れでもあるの?」
小競り合いも大規模な戦闘も今まで何度もあった。
そのたびに武器を取っておいたのでは保管場所がなくなってしまう。
「それはな、俺が初めて殺しをやったときの相棒なんだ。
賊になって、もう何があってもまともな世界には引き返せねえて
身体が痺れるような覚悟をくれた奴さ」
「なるほどね。これは君の覚悟の証ってわけだ。
そうさ、僕らはもう娑婆には戻れない。戻る気もないけどね」
「今更普通に暮らせって言われても無理だろうし。
そもそも陸にいるのが落ち着かねえよ」
杯に残っている酒を呷って、マンゴジェリーは満足そうに息を吐いた。
スキンブルシャンクスも杯を干す。
「もう一杯どうだい?君の掃除の腕と覚悟に乾杯だ」
「悪くねえ」
二つの杯は再び酒で満ちた。
ほろ酔い気分の男たちの、本日二度目の乾杯。
飄々としてるけど、マンゴだって最初は怖かったんじゃないかと思う。
グロールタイガー船きっての切れ者二名の酒盛りをお届けしました。
涙雨
涙雨
甲板に上がったらしいマンゴジェリーの素っ頓狂な声を聞いて、
ミストフェリーズとマンカストラップも甲板に出てきた。
「どうした?うわっ、こりゃすごい」
顔を出した途端にずぶ濡れになるような大雨にマンカストラップは思わず頭を引っ込めた。
舳先すら霞んで見えるほどの土砂降りで、マンゴジェリーは既に海に飛び込んだかのような有り様だ。
「スコールなんてもんじゃないね。これは暫く続きそうだよ」
そう言いながらミストフェリーズは甲板に出て行く。水に濡れるのが厭では海賊などできない。
ただ、確かにいつになく強い雨は甲板を叩きつけて大きな音を鳴らしている。
台風の時は一時的にこれくらい激しく降ることもあるが、
雨だけでなく風も強くて危険だからどこぞの港や島影やらに停泊していることが多い。
「冷える季節じゃなくて良かった良かった」
「水は貯めとく?」
「いらねえよ、もうどの桶も一杯だ。おいマンカス、何気持ち悪い顔してんだよ」
マンゴジェリーの口の悪いのは今に始まったことではないが、
気持ち悪いと言われたマンカストラップは反射的に眉を顰めた。
「もう少し言い方があるだろう?」
「おう、わりい。つい本音が出ちまった。で、どうしたんだ?」
まるで悪いと思っていないようなマンゴジェリーの軽口には諦めたように溜息を吐き、
マンカストラップは手をかざして分厚く低空に立ちこめた雨雲を仰いだ。
「ちょっと思い出していた、ギルバートのことを」
「ギルバート?そういや大層ご活躍らしいね、こないだ寄ったとこで名前聞いたよ」
「ほう。まあ、活躍してもらわないとな。船長の名が廃る」
「そりゃいいけどよ、何で急にギルバートなんだ?」
土砂降りの中、マストの具合を確かめに甲板を歩きながらマンゴジェリーが訊く。
僅かに足を引き摺りながら、マンカストラップは苦笑を浮かべた。
「あの男は生真面目で色恋なんてものにはとんと縁が無さそうだが」
「や、それはマンカスに言われたくないと思うよ」
「煩いぞミスト。とにかくだ、そんな奴の口から雨にまつわる話を聞いてな」
それは、ギルバートの指揮する船に潜り込んで一年が巡ろうとしたある日。
時期はちょうど今くらいだったはずだ。
「見張りで甲板に出ていたら雨に降られてな、まあそういう時期だから仕方ないが。
ちょうどそこにギルバートが姿を見せて、何を思ったかにこにこと話しかけてきた」
「向こうも俺らの正体には気付いていただろうからな、カモフラージュだろ」
「だろうな。で、その時に持ち出してきた話だ」
雨で見通しの悪い海上をゆるりと見回して、ギルバートはのんびりと話し出した。
牽牛と織女の話は聞いたことがありますか、と。
ありません、とマンカストラップは即答した。
「織女は機織りの女性でひたすら機を織っていたそうだ。
機織りばかりで可哀想だと思った彼女の父親が牽牛という名の男性に引き合わせると、
今度はその男に夢中になってさっぱり機を織らなくなったのだという」
「その織女とやらにほどほどって言葉を教えてあげたいね」
雨に濡れてぎっちりと締まっている帆柱のロープを確認しながらミストフェリーズが言う。
「全くだ。そんで?その周りが見えなくなるタイプのお嬢さんがどうだって?」
雨でもお構いなく帆柱によじ登ってマストの状態を見ているマンゴジェリーが
足許にいるマンカストラップに怒鳴るように続きを促す。
あまりに雨の降りしきる音が騒々しくて、大声でなければ相手に聞こえない。
「結局また親父さんに引き離されたってさ。河のあっちとこっちに。
その河ってのがあの天の川だそうだ」
「親父さんも困ってたんだろうけど、自分で引き合わせといてまた引き離すってどうなのさ。
振り回されっぱなしの牽牛って男に僕は同情しちゃうね。マンカスはどう?」
「俺は知らん」
「朴念仁だもんなあ、マンカスは。訊くだけ無駄だぜ、ミスト」
煩いとマンカストラップは怒鳴るが、ミストフェリーズはそれもそうだねと呟く。
「貴様ら、さっきから俺をバカにしてないか?」
「してないしてない、客観的に見て真面目だなって褒めてるよ。ねえ、マンゴ」
「その通り。じゃなきゃあんたに船の頭任せたりしねえって」
派手な水音を立てながら甲板に飛び降りたマンゴジェリーは、悪びれもせずにへらりと笑った。
「調子の良い奴だな、相変わらず」
「お褒めにあずかって光栄なことで。それよか続きは?
まさか、引き離されちゃいました終わり。なんて言わねえだろう?」
「それはない。引き離されたが、ふたりは年に一度だけ逢うことを許された」
そう言ってマンカストラップは足許に跳ねる雨に目を落とした。
釣られるようにミストフェリーズも甲板に視線を落としている。
「この雨は織女と牽牛が再会の喜びに涙し、別れに涙しているのだという。
だから、この季節には雨が多いのだということだ」
「・・・この話を、あのギルバートが?」
「故郷にある伝承なのだそうだ」
何故ギルバートがこんな話をマンカストラップにしたのかは分からずじまいだ。
他に当たり障りのない会話が成り立つような話題が無かったのかもしれない。
そして、この話はマンカストラップの記憶に残り続けている。
雨が降るとたまに思い出す。
「よその国ではこのふたりの邂逅を祝う風習もあったりするそうだ」
「へえ。見たこともない男女のために祝うなんて気の良い奴らもいるんだな」
「そうだな。願掛けもするそうだ。織女さんのように手習いが上手くなるように」
この願掛け云々の話はギルバートからではなく、博学の仲間から訊いた話である。
「僕も何か願い事しようかな。こないだ手に入れた横笛吹けるようになりたいし」
「いいかもしれんな」
話を終えて、ギルバートは呟くように言った。
明日は晴れるといいなと思うんです。
再会に噎び泣く訳でなく、別れに慟哭するでなく、
ただ楽しく穏やかに戯れていると思うとちょっと嬉しくなるでしょう、と。
「・・・明日は晴れるといいな」
「そうだね」
「そうだな」
くるりと踵を返し、船室に向かって歩き出したマンカストラップを
ミストフェリーズとマンゴジェリーが追う。
「着替えてから一杯やろう。さすがにこのままだと冷える」
「お、いいねえ」
この雨なら海軍に見つかることもない。
少しばかり前に手に入れた旨い酒の味を思い出しながら
マンカストラップは頭に巻いたバンダナを無造作に引っ剥がした。
濡れた布は、とてもじゃないが結び目をほどくなんてできない。
ほとんど無意識に絞った赤と白の布からは、どこにあったのかと思うくらい大量に水が滴った。
七夕頃に書いた話。本編後のお話ですね。
シャム国は雨期か乾期しかないと思いますが。
と、自分にツッコミを入れる。