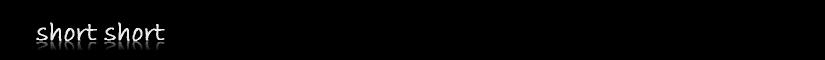小島にて
小島にて
遠浅の海はエメラルドグリーンを湛え、延々と続くように見える白い砂浜を洗っている。
その浜をずっと行ったところに入り江があって、大小の舟が停泊していた。
この小さな島で唯一の港町はそれなりに賑わっていて活気もある。
新鮮な魚や果物を売り捌く元気な声が響き渡っている。
「ここはいつ来ても美しいところですね。皆活き活きとしているし」
「そうだな。こんなにも明るいのに、どこか穏やかでほっとする」
視察で島を訪れていた東方司令部司令官のアロンゾは、
部下の若い男と並んで窓から賑わしい港町を眺めていた。
「海賊が襲撃してくるという件についての調査はどうなっている?」
「海陸両方から調査中です。暫しお待ち下さい」
アロンゾは頷いて窓にもたれ掛かった。
彼らがいるのは島にある海軍東方司令部の出張所だった。
建物自体は周りの家々と変わらない石造りだが、周りは平屋が多く
二階建ての海軍の建物からは街から海まで一望することができる。
大きな窓は全開にされ、吹き抜ける風は常に潮の匂いがする。
出張所に勤める兵たちはどこかのんびりとしていて、
付近の漁民や商店の主らとも顔見知りで仲も良いようだった。
「無防備なほどだが、この島にはこれくらいがちょうど良いのかもしれないな」
衛兵が酒場の店主と笑い合っている様子を見て、アロンゾは目を細めた。
「海賊共がここに来てものんびりしたくなるんじゃ・・・」
「司令官?どうかされましたか?」
アロンゾの目が不意に鋭くなったのを見て、若い部下は戸惑いながら上官の視線を追う。
「あの、男」
「あの男ってどの男です?あ、ちょっと司令官!」
部下が振り返った時には、彼の上官は既に背後の階段を半ばまで下りていた。
慌てた部下の下士官が体勢を崩している間に、アロンゾの姿は見えなくなった。
一方、階下ではアロンゾの副官が出張所の仕事状況を軍員らに質問していた。
その副官は、すごい勢いで階段を駆け下りてきた上官を唖然として見送った後、
転がるようにして下りてきた部下の下士官を捕まえた。
「どうしたんだ!?」
「それが・・・」
緊張した面持ちの副官と心配そうな表情の軍員立ちを見渡して、
下士官は申し訳なさそうに首を竦めた。
「・・・わたくしにも全くわからないのです」
アロンゾが息せき切って飛び込んだ酒屋は、昼間から陽気に飲み交わしている老若男女の声と
酒や肴の匂いが入り交じり、熱気でむっとしていた。
やはり窓が全開になっている木造の建物は、強い風が吹けば壊れそうなほどに粗末だった。
実際、何年かに一度は大嵐で大破することがあるのだという。
それでも何故か看板だけは壊れることも失われることもなく、
再建するたび入り口の上に掛けられている。
「おやあ、海軍の旦那。えらく急いでるね」
「これは失礼しました。ちょっと知り合いを捜していまして」
「そうかい、まあ広くない店だけどゆっくり探してくれ」
頭を下げた品の良いアロンゾの態度に酒場の主も気を良くしたようだ。
酒場に集まった客たちは、地位の高そうなアロンゾの同行をあからさまな興味を持って観察している。
「ここまで見られていると居心地が悪いな・・・っと、いたいた」
独り言を零したアロンゾの目が、窓際の席で独り杯を呷っている男のところで止まった。
特に声を掛けることもせずにその男の前の席に腰を下ろすと、
アロンゾの気配に気付いたのか、男は窓の外に向けていた目を正面に戻した。
「お前・・・」
絶句して口が開いたままになった男に向けて、アロンゾは柔らかな笑みを浮かべた。
「久しぶり。名前は・・・何だっけ?忘れたな」
「忘れるも何も、名乗ったことがねえよ」
酒場の主が置いていった杯に酒を注いでアロンゾの方に押しやりながら、男は苦々しく呟いた。
「困ったな、業務中なんだ。酒など飲んでいると部下に示しがつかない」
「ああ?ここらの海軍連中は勤務中だろうが普通に飲んでんじゃねえの?
こんなもん、酒か水か果汁かわかりゃしねえしな」
杯に並々と注がれた液体は見事な山吹色をしている。
ゆらゆらとゆれて南国の果実の匂いを漂わせていた。
「それじゃあいただくとしよう」
「そうこなくっちゃな」
杯を手にしたアロンゾは、一息に中身を飲み干した。
豪快とも言える飲みっぷりだが、その杯を台に置くまでの一連の所作はあくまで優雅だった。
「アンタもお気楽なもんだな。毒でも入ってたらどうすんだよ」
「その時はその時だ、仕方あるまい。それに、今のは毒を入れるタイミングがない。
ここの主はそんなことをしても利が無いし、
誰も俺がここにくることは予想できないから用意もない」
「はいはい、その通りですよ。言っとくけど、俺はここで何もしちゃいないぜ。
これだって金払って飲んでんだ、海軍の偉いさんにいちゃもん付けられる筋合いはない」
訝しがるような表情の男に、わかっているよと言ってアロンゾは立ち上がった。
酔った様子もなく相変わらず穏やかな笑みを浮かべて、付き合ってくれないかと言う。
「アンタひとりか?」
「ひとりだ、部下は置いてきた」
「だったら付き合ってもいい。こっちはほぼ丸腰だからな」
「ほぼ、か」
微苦笑を浮かべて、アロンゾは先に立って歩き出した。
酒場の客たちは、海軍士官と漁師風情の男が連れ立って出て行くのを不思議そうに見送ったが、
その姿が見えなくなるとすぐにいつもの喧噪が戻ってきた。
波打ち際をのんびり歩いていたアロンゾは、半歩後ろの男に顔を向けた。
「本当に久しいな。司令部で会って以来か。あの頃はまだ海軍の制服を着ていたか」
「よく覚えてるよな、本当にあれっきりだったってのに。
まあ俺も覚えてるぜ。お坊ちゃん司令官のアロンゾ中佐だろう?」
「あまり嬉しくない覚えられ方だが、事実だから仕方ないな」
苦笑しつつ、木陰を見つけたアロンゾはそこで足を止めて平たい石に座った。
「その赤毛が妙に目に焼き付いていた。
グロールタイガーの腹心じゃないかと聞かされていたから余計に印象的だった」
「この赤毛の所為で散々からかわれたもんだぜ。
俺はマンゴジェリーだ。元ギルバート軍の整備士の」
にやりとしたマンゴジェリーは、立ったまま海軍の司令官を見下ろした。
「そんで?アンタは何の用なんだ?」
「話したかっただけだが、仕事上確認しておきたいこともあってね。
この島を海賊が襲撃するという情報がある、そっちにそのつもりがあるのか探ろうと思って」
「そのつもりだったら言うわけねえし、見つかるような場所で酒なんか飲まねえよ」
呆れたように溜め息を吐いたマンゴジェリーは緑色の海に目を向けた。
「その海賊は来ないぜ。俺らが狩っちまった」
「狩った?グロールタイガー一味が狩るほど旨そうな獲物だったのか?」
「そうじゃねえけど」
がしがしと頭を掻くマンゴジェリーのよれた服の袖口から包帯がちらりと覗いた。
何かする度にぎこちなく手を止めたりするのは傷の所為らしいとアロンゾは納得した。
「この島は俺らが骨休めに使ってるからな。他の奴らに手を出されたくはねえ。
だから狩った。簡単な話だろう?」
「簡単だが物騒な話だな。だが、そういうことであればこの島は暫く平和だろうな。
グロールタイガー一味の縄張りと来たらそう簡単に手は伸ばせないだろう」
「どうだかな。頭がいなくなってちょっかいかけてくる輩は増えたぜ。
あの男はいかれてたし自分勝手で荒くれだったけど、すげえ奴だったって今は思う。
腹心の俺らですら怖かったんだ、周りが縮み上がるのもわかるってもんだ」
グランブスキンも死んじまったしな、と言いながら
マンゴジェリーはひょいと大きな石に飛び乗ってそこに腰を下ろした。
「アンタは」
アロンゾの整った横顔を見ながら、マンゴジェリーは思い出したように呟いた。
「ランパスの弟だってな。似てないな」
「確かに兄弟だな、腹違いだけれども。似ていないと言われたのは初めてだが」
「見た目のことじゃないぜ。てアンタはお上品だし頭も良さそうで、一見して貴族って感じがするぜ。
あの口も目つきも悪い男はどう見たって貴族じゃねえよな。
身分の低い兄なんて邪魔なだけじゃねえの?なのにアンタはあの男を嫌ってねえ」
驚いたようにアロンゾはマンゴジェリーの方を見た。
「何故、嫌っていないと言える?」
「俺がアンタのことランパスの弟だって言ってもイヤな顔しなかったからな」
「参ったな、鋭い男だ」
僅かにアロンゾの口から零れた苦笑の音は、絶え間なく流れる風にすぐにかき消された。
視線を巡らせて透き通った海を見つめるアロンゾの目に寂しさを見て、マンゴジェリーは眉を寄せた。
「俺は兄のことをほとんど知らない」
唐突に、独り言のようにアロンゾは話し出した。
「愛想が悪くて強面だけど、意外に面倒見の良い兄貴気質で、
刀剣の腕前も体術も目を見張る物があるのに本業の舵取りの腕前は怪しい」
「知ってるんじゃねえか」
「聞いた話だ。俺自身はそれが本当かどうか知らない。
兄とは話すことも無ければ、小さい頃は顔を合わすことさえ滅多になかった。
気付いていたようだが、確かに母方が貴族の俺は貴族で兄は違う」
妾腹だから、とアロンゾは呟くように付け足した。
「貴族様のアンタにとっちゃ、そんな腹違いの兄貴なんていないも同然だろ?
何をそんなに憂える必要があんだよ。哀れんでんのかよ」
「・・・兄と父だけだったんだ」
寂しそうな笑みの中に懐かしむような色を浮かべてたアロンゾは海から目を離した。
「兄と父だけが俺を褒めてくれた」
くるりと向き直ったアロンゾと目が合ったマンゴジェリーは、無言で続きを促した。
「名家の子だから何でもできて当たり前、みんな俺をそんなふうに見ていた。
学問も剣術もできて当たり前、一番で当然と思われていた。期待に応えることは俺の義務だった。
新しいことを覚えても、何かできるようになっても、誰も褒めてはくれなかったんだ」
「ふうん。名家に生まれるってのも疲れるんだな。アンタよくぐれなかったよな。
俺なんか、ちょっと良いもん盗ってきたらダチがすっげえ喜んで褒めてくれたぜ」
「それは羨ましいことだ」
悪びれないマンゴジェリーの言葉に、アロンゾは声を立てて笑った。
「母が留守の時など、父は時々兄を伴って来てくれた。
兄は剣術の練習に付き合ってくれて、全く歯が立たない俺のことを褒めてくれた。
腕を上げたな、太刀筋が良くなっている、よく頑張っているってな」
「何とも月並みでおもしろみのない褒め言葉だな。あいつらしいけど」
「そうだな。眉一つ動かさないで、それでもその言葉一つ一つが俺には凄く嬉しかった。
あの頃、兄が褒めてくれた言葉を忘れたことはない」
「俺は逆だな」
小石を弄びながらマンゴジェリーが言う。
どういうことだとアロンゾは小さく首を傾げて問うた。
「俺は、叱られた言葉を忘れたことがない」
「叱られた言葉?」
「そ、憲兵に説教された。名前も知らねえし顔も覚えてねえけど。
俺は物心ついた頃からスラム暮らしでね、今思えばそりゃ酷い暮らしだったぜ。
犯罪の巣窟みたいなとこでさ、誰かが死んだって話には事欠かねえし殴り合いの喧嘩も珍しくない」
眉を顰めるアロンゾにニヤリと笑って、マンゴジェリーは手にしていた小石を放り投げた。
そしてまた別の小石を拾い上げて弄り始める。
「俺は盗みやって食いつないでた。ガキはみんなゴミ漁りか盗みでしか食えなかったんだ。
俺は相当盗みの才能があったけどさ、それでも何回か憲兵に捕まったもんだ。
奴ら、罵りながら蹴るわ殴るわで満足するから、ちょっと痛いの我慢してりゃよかった」
「酷いものだな」
「アンタ一回自分の目で見てみたらいいぜ。あそこで生きてる奴らってのは強かなんだぜ。
罵られて殴られるだけじゃスラムの悪童は懲りねえよ。
そんなの日常茶飯事だしな。けどさ、一回だけ俺らは罵られなかったことがある」
驚いたぜ、とマンゴジェリーはからから笑う。
「その憲兵は俺らに拳骨くれた後説教しだしてさ。俺もダチも変な顔してたと思うぜ、
罵倒されるってことはあったけど、怒られるとか叱られるってのはそれまでなかったからさ」
「その憲兵は何を言ったんだ?」
「君らは凄い身体能力を持っているのに、
なぜそれを盗みを止めて真っ当に生きるために使えないのかってさ。
そう言われたときは、俺ももしかしたら真っ当に生きられるかもと思った」
思っただけで現実にはならなかったのだ。
アロンゾの前にいるマンゴジェリーは無く子も黙るグロールタイガー一味の海賊なのだから。
「結局俺は海賊になっちまったし、今はもう世間様が真っ当だと信じている生き方に興味もない。
アンタも海軍は辞めねえだろうし、生涯敵同士だろうよ」
「そうだろうな。ただ、俺は世に言う真っ当な生き方だけが良いとは思わない。
勿論、海賊行為は絶対に良いとは言えないが」
「真っ当な道から外れざるを得なかった奴らもいるんだ。
最初っから真っ当な道を行ってる奴らばっかりに良いことがあるのは不公平過ぎるってもんだ。
世間的には真っ当と言えない暮らしだって良いことはある」
手にしていた小石を遠くに放り投げながら、マンゴジェリーは言った。
アロンゾはただ頷く。
「あの憲兵は何者なんだろうな。声すら覚えてねえ。
それでも、あの憲兵が俺を叱った言葉はずっと覚えていた」
「なるほど。叱られた言葉を忘れたことがないとはそういうことか」
「そういうことだ・・・っと、アンタ探されてるんじゃねえの?」
マンゴジェリーは海のさざめきの合間にアロンゾを呼ぶ声を聞いた。
首を傾げたアロンゾにも、暫くして部下が彼を呼ぶ声が聞こえてきた。
「そういえば行き先も告げずに来たな」
「それでいいのかよ、海軍中佐さんよ」
「残念」
立ち上がったアロンゾは、小さく笑みを浮かべて肩章を指し示した。
「大佐になったんだ。知っておいてくれると嬉しいよ、マンゴジェリー」
「そりゃあ失礼、大佐殿」
手も使わずに岩の上にひょいと立ち上がったマンゴジェリーは、
アロンゾの部下らしい若い男性軍員がきょろきょろしているのを眺める。
「ところで大佐殿」
「うん?」
「そのダガー珍しい型だから見覚えあんだけど、ボンバルリーナと揃えてんの?
もしかして付き合ってる?」
「全く、本当に鋭いな」
鞘に収めたままの短剣をベルトから抜き取って、アロンゾはそれを愛おしそうに見つめた。
「その通り、彼女とは長い付き合いだ」
「ふうん。彼女にダガー送る風習とかあんだ?貴族様ってのはロマンチストだねえ」
「良い趣向だと言って貰えるかな?」
片眉を持ち上げてみせるアロンゾをみて、マンゴジェリーは喉の奥で笑った。
「アンタ、そんな顔してたらあの無愛想な兄貴とそっくりだぜ。
他の海軍の奴らに見つかったら面倒だから行くぜ。
まあ、せいぜい頑張って兄貴と仲良くするんだな」
「何とかするさ。付き合ってくれてありがとう。今日の酒代はいずれ何らかの形で返そう」
「おう、三倍返しくらいでよろしく」
軽く跳躍したと思えば、身軽に岩棚に取り付いてよじ登っていくマンゴジェリーに感心していたアロンゾは
部下がすぐ背後で彼を呼ぶ声でようやく我に返った。
「司令官!おひとりで出歩かれるなど以ての外です!海賊が来るかもしれないというのに!」
「すまない、少し急いでいたんだ。海賊の件について聞き込みをしていた。
海賊については心配しなくて良さそうだ。念のため、もう少し留まって様子は見るが」
「畏まりました。ともかく戻りましょう。みんな吃驚していたんですから」
部下の不満を軽く受け流しながら歩いて行くアロンゾたちの声を聞きながら、
ゆらゆら揺れる薄緑の海をただじっと眺めた。
綺麗な海だった。彼が知ってるゴミだらけの海ではない。
「俺にはアンタを煩わすようなしがらみってもんが無い。
せいせいするぜって言いたいとこだけど、しがらみを知らねえからせいせいするも何もねえか。
一度くらい、そういうもんを手にすることがあっても良かったのかもな」
しがらみなんてロクなもんじゃないし盗めるものでもない。
でも、手に入れられないのは盗みの名手を自認するマンゴジェリーには少し癪だった。
もう一度飲み直そうかと独りごちて、マンゴジェリーは海に背を向けて歩き出した。
TOPに置いた時は長すぎて二分割しました。
アロンゾとマンゴジェリーなんて、どこにも接点ありませんね。
本編でも一回顔見たくらいだと思いますが、ふたりとも良く覚えてたなあ。