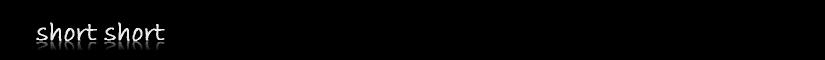ドリアン * new *
ドリアン
拠点となっている南方司令部から船で三日ほどの寄港地で、隊員たちは束の間の休息を取っていた。
市場のある賑やかな港町だ。
休息と言っても、ジェミマやタントミールが食料や薬草の買い出しをしている間のことなので、
当然ながら海軍の制服を着用していのだからハメを外すわけにはいかない。
ここに立ち寄る海軍員たちは少なくないようで、市場の売り子も客も、
制服を着た隊員たちがいたところでさほど気にする様子はない。
店主たちはむしろ、積極的に声を掛けるほどだ。
体力勝負の海軍員たちはよく食べるから、売り手にしてみればたくさん買ってくれる上客である。
ギルバートはコリコパットと連れだってさっさと行ってしまい、
マキャヴィティは買い出しに付き合うと言ってジェミマたちに付いていき、
タンブルブルータスは見張りのために船に残ることになっている。
女性たちは楽しそうに出掛けてしまい、港に降り立ったは良いものの、
カーバケッティはぽつねんとその場に立ち尽くしていた。
「・・・まあ、いいか。タンブルに何か買ってきてやるかな」
市場には数々の食料が売られているはずだ。
勿論、生活に必要な品々は他にも売られているが、さし当たり必要なものは既に揃っているので、
欲しいものがあるとしたら、船上で口にできない新鮮な果物などだ。
立ち寄りの時間が短いから酒は飲むなとギルバートから言われている。
「発酵した果物も要注意、だったな」
市場に置かれている果物は、新鮮なものから腐る寸前の熟したものまで様々だ。
気温の高いこの国では、果物はすぐにしなびてしまう。
時折、そのまま発酵してしまうものがある。
これを食べてしまうと、酒を飲んだのと同じ状態になりかねない。
料理もできるカーバケッティは、当然そんなものを掴まされるヘマをすることはない。
「今日は何か珍しいもの出てるかな」
「おい」
制服の内ポケットに硬貨が入っているのを軽く叩いて確かめたカーバケッティは、
声を掛けられて市場に向かおうと一歩踏み出した体勢のまま振り向いた。
「お、ランパス。起きたのか?」
「ああ、まあな。ジェニーさんが掃除したいからって」
「追い出されたわけか。俺は今から何か食いに行くけど、ランパスも行くか?」
カーバケッティが訊ねると、ランパスキャットは欠伸をしながら頷いた。
いい歳した男同士で食い歩きなどもの悲しいというよりむさ苦しいだろうが、
軍というのは大抵が男ばかりなので傍から見れば違和感は無いはずだ。
「喉が渇いたから何か飲むものが欲しいな。酒はダメなんだろう?」
「隊長がダメだって言ってた、いつもの通りだ。あ、ココナッツ椰子売ってるかも」
威勢の良いかけ声が飛び交い、そこで売られている者を求める客でごった返す市場は、
ただでさえ汗ばむ陽気の中でさらに熱気を孕んでいる。
「兄さん、そのココナッツ椰子一つ貰える?あ、そっちじゃなくてこれがいいかも。
二つの容器に分けて入れてくれる?うん、それでいいよ。はい、お金」
目を付けた屋台でカーバケッティはココナッツ椰子を一つ購入した。
目の前で切られて注がれるココナッツのジュースは甘く香った。
「うまそうだ」
「間違いない筈だ」
カーバケッティが手にしている二つの容器の内側で、
透明な液体が太陽の光をはね返して煌めいている。
一つの容器をランパスキャットに差し出し乾杯をする。
「甘くて美味しい。香りもすごく良いし」
「久しぶりの味だ」
それぞれに満足そうな表情を浮かべて、カーバケッティとランパスキャットはさらに歩を進めた。
ココナッツジュースでは栄養補給ができてもカロリーは補えない。
これから船を出すという体力仕事が待ち受けているだけに、
エネルギーになるものが欲しいところだ。
「お、タマリンド。サントルもあるってさ。マンゴーもあるけど」
「うまいなら何でもいい」
「相変わらず無粋だな、ランパス。せっかくこんなに美味しそうなものがあるのに。
マンゴーはあの青いやつに唐辛子とか付けて食べると最高なんだぞ」
「へえ」
熱弁を振るうカーバケッティに、ランパスキャットは形ばかりの相槌を打つ。
食材に関する知識は豊富だ。
当然良いものの選び方もよく知っているし、調理方法もわかっている、
それも幾通りもの調理方法が頭に入っているという変わり者参謀官が、
なぜ調理師でなく参謀官の道を選んだのかランパスキャットは時々疑問に思っている。
「やっぱりタマリンドかな・・・っと、ドリアンがあるじゃないか」
「ドリアン?あれって珍しいのか?」
「別に珍しくはないけど、ちょっと値が張るからあんまり食べたりしないだろう?
これ、おいしそうだな。精力も付くし、これにしようか」
相談しているようで独断である。
だが、ランパスキャットに文句はない。何であれ美味しければいいのだ。
並んでいる果実を手早く吟味して一つ取り上げたカーバケッティは、
店主に皮を剥いてくれるように頼んで金を払う。
談笑しながら手際よく実を捌いてくれた店主の「またどうぞ」という声を聞きながら、
カーバケッティは皿代わりの大きな葉に載せられたドリアンの剥き身を差し出した。
「かなり良い具合だ、この濃厚な旨味がたまらないんだよな」
「確かにうまい。これでこの匂いじゃなけりゃ最高なんだが」
「言うなよ、この香りこそドリアンじゃないか。まあ、匂うのは匂うけどな」
ぺろりと指先を舐めたカーバケッティは、ふと何かを思い出したように真顔になった。
そして、隣でもごもごと口を動かしている同僚に目を向ける。
「なあランパス、俺はマヌケだった」
「そんな今更何を」
「否定してくれよ!じゃなくて!あの時俺は気付くべきだったんだ。
学生時代のあの異臭騒ぎ、どう考えたって原因はお前だろう?」
唐突な話題だ。
学生時代など記憶の彼方となっているランパスキャットは逡巡した挙げ句に首を傾げた。
「そんなことあったか?」
「あった。ある日、何故か寮の部屋から凄い匂いがして大騒ぎになったんだ。
お前はその日から海に出てたからもしかしたら知らないのかもしれないけど、
その原因が放置されたドリアンの種だったっんだ。しかも俺の部屋にあった」
「ほう。で、何で俺が原因なんだ?俺がわざわざお前の部屋に種を置いていったとでも言うのか?」
「その通りだ!俺は身に覚えのないことですげえ顰蹙買ったんだからな」
カーバケッティとランパスキャットは海技学校の同期生である。
共に周りから浮くような存在だった所為か、何となく一緒にいることが多かったのだ。
戦場にかり出されることの多かったランパスキャットを、
世話焼きのカーバケッティが何かと構っていた所為もある。
何かと口うるさいカーバケッティと不精者のランパスキャットのことだから、
つまらない口論になることもたびたびあったものだ。
ただでさえ変わり者扱いされることの多かったカーバケッティは、
彼なりにあまり目立たないように日々を過ごしていたのだ。
それが突然異臭騒ぎの原因にされたのだから忘れろと言われても無理な話だ。
「あれは絶対お前の腹いせだろう?だいたい、ドリアンなんて高価なものは学生には手が出ない。
それに引き替え、ランパスは海に出てたから手当だって貰ってたはずだ」
「そりゃまあ仕事したんだから、代価を貰うのは当然だな」
「そこに不満はない。けど、嫌がらせの手段が姑息だ」
大きく溜め息を吐いて、カーバケッティは甘い果肉にかぶりついた。
思い出すと今でさえ腹は立つが、美味いものは美味い。
蕩ける甘さに、怒気も蕩けてゆく。
「あの頃は放置した種がそんなに匂うもんだとも思ってなかっただろうから許せ」
「まあ、今となっては事実は確かめようもないしな。あと一切れ、食っていいぞ」
「じゃあ遠慮なく」
残っていた一切れをひょいと口に放り込むランパスキャットを横目に、
カーバケッティは再び店を物色し始めた。
「何か探してるのか?」
「うーん・・・タンブルに何か買って帰ってやろうかと。あいつ何が好きだっけ?」
きょろきょろとしているカーバケッティの後ろを付いて歩きながら、
ゴミの集積場所を見つけたランパスキャットはそこに葉と容器を纏めて捨てた。
「タンブルの好きなもの?魚と船とカッサじゃないのか?」
「そういう答えは求めてないってわかれよ」
そこそこ真剣に答えたランパスキャットの言葉を一蹴して、カーバケッティは更に歩いて行く。
「なあカーバ。食い物はジェミマたちが買ってくるだろうし、もっと他のがいいんじゃないのか?」
「それもそうか。じゃあ釣り竿でも買ってってやるか」
「さっき向こうの店に売っていたな。買いに行こう。
ついでに、お前も欲しいものがあったら一緒に払うから言えよ」
「異臭騒ぎのお詫びか?まあ、見てから考えよう」
カーバケッティとランパスキャットは来た道を取って返して目的の店に向かう。
途中、屋台で何かを食べながら行商たちと談笑しているギルバートたちが見えた。
何気なく交わす言葉の中から情報を得るのも仕事の一環だ。
物腰の柔らかいギルバートと開けっぴろげなコリコパットならば、
例え海軍の制服を纏っていても相手の警戒心はすぐに解かれてしまうはずだ。
異民族とすぐにわかってしまい敬遠されるカーバケッティと、強面のランパスキャットでは、
疑り深い行商たちから重要な情報を聞き出すのは難しい。
「市場の客たちはみんな俺たちから心持ち距離を取っているようだな」
「そりゃあ視察に見えるからじゃないか?お前が強面だからかも。取って食いやしないのにな」
道の真ん中を歩きながらカーバケッティとランパスキャットはちらりと目を合わせて苦笑した。
もう慣れたことだ。
今はこの状況を楽しむ余裕すらある。
さほど階級は高くないのに、何を避けずとも堂々と道の真ん中を歩けるのだ。
「タンブルとマキャとランパスで歩くといい。たぶん今よりも道が広く使えるはずだ」
「いや、俺らが揃うと隊長が不機嫌になるから止めておこう」
「それもそうだな」
互いに乾いた笑いを零し、ランパスキャットとカーバケッティは雑貨を並べる屋台に歩み寄ると、
よく日に焼けたがたいの良い店主に声を掛けた。
「おっちゃん、釣り竿ちょうだい。長いやつにしてくれ」
カーバは決して根に持つタイプではないのですが、
とんでもない置き土産が強烈に脳裏に焼き付いているようです。
ドリアンは種だけでも相当匂うらしいですね。
忘れられない旋律、あるいは戦慄
忘れられない旋律、あるいは戦慄
大音量で管楽器を吹き鳴らしすように、窓の外では風が吹き荒れている。
強弱と高低はしっかりとあるくせに、
拍子だけはまるで無秩序な激しい演奏は夜明け前から一向止む気配はない。
こんなにけたたましい変拍子の嵐でも、海は目一杯踊り狂っている。
いや、踊りたくてそうしているのではないのだろう。
でも、海は沢山の白波の腕を伸ばして舞っている。
その腕に引っ張られて海に沈んだ船はどれほどになるだろうか。
「私たちの船はアナタの誘いには乗らなかったんだから」
ガタガタ鳴る窓の傍に立って海を眺めていたカッサンドラは思わず呟いた。
いるべき場所を失ったあの日。
船は海に沈めた。
傷ついた船を穏やかな海に水葬にした。
決して波に呑まれたわけじゃない。
「風が唸るとカッサは哀しげな目をするのね」
「カーバにも言われたわ。そんなに憂えた顔をしているかしら」
「普通を装えているんじゃないかしら。でも、私たちは付き合いが長いし」
絡まった包帯を巻き直しながらディミータは呟くように言った。
ただ付き合いが長いだけじゃない。その哀しみの理由を知っている。
悲しい記憶を共有しているのだ。
「忘れたいと思ったわ」
痛みに似た哀しみを。
慕った上官と先輩隊員たちを喪った苦しさを。
「でも、自分の記憶なのに自分では消せなかった」
「それはね、カッサがどこかで忘れたくない、忘れちゃいけないと思っているからよ。
それから、カッサ自身かその痛みを乗り越えられると判断したからね」
忘れなければ壊れてしまうのならば、身体はその記憶を封印してしまう。
「喪ったものは多かったかもしれない。
ただ、あの日が齎したものも多いから忘れたくないと思うのかもしれない」
カッサンドラは手を伸ばしてディミータに触れた。その華奢な手は僅かに震えていた。
「カッサ、一度味わった恐怖は消えやしないわ。激しい雨風に不安が募るのは私も同じよ」
ディミータはカッサンドラの手を強く握った。
「本当に大切なものを喪うかもしれないと心底恐怖したことは今でも蘇るわ。
時々、本当にみんながここにいるのか温もりを確かめないと不安になるの」
「ディミは強いから大丈夫なんだと思っていたわ。ごめんなさい」
「謝ることないでしょ?カッサだって口には出さないじゃない」
「表情に出ているみたいだけど」
カッサンドラとディミータは目を合わせてクスクスと笑った。
「大丈夫、みんな気付いていないわ」
気付いていても気付かない振りはしてくれる。
みんな、触れたら痛む過去の傷の一つや二つは抱えている。
気づくべき時には誰かが気付いてくれる。
「怖いのは弱いからじゃないわ。私たちは生き残ったの、死の恐怖を間近にしながらね」
うねる海 軋む船 血の匂い 死の跫音
戦慄
「誰かの分まで生きる余裕なんてないけど、恐れと哀しみを抱いたままでも
私は自分の命を生きられることに感謝したいと思うの」
「あの時はそうは思えなかったけど、生きていて良かったと今なら感じるわ。
そう思わせてくれるだけのものがあるもの」
喪ったものはあまりに多かった。
ほんの少し残った大切なものを掻き抱いてうずくまっていた日々。
そして前を向いて立ち上がった時。
「生きられるわ。怖いことはたくさんあるけど」
「泣いたっていいのよ。場所と時間くらいなら提供するわ」
「あら、一緒に泣いてはくれないの?」
忘れない、忘れられないから。
身体が覚えてしまった恐怖は幾度となく蘇っては哀しみを思い出させる。
それでも今、記憶の中にしかいない仲間のもとに行きたいとは思わない。
「少しずつ痛みも哀しみも薄れていくけど決してゼロにはならないから
もし私が泣いた時は傍にいて掴まらせてね」
「私でいいの?」
「男の子に涙は見せたくないでしょう?」
それもそうね、とディミータが苦笑する。カッサンドラは楽しげに笑った。
「風に呼ばれて波に招かれたとしても、私はまだ彼岸には行かない」
「カッサが行ってしまったら男たちが半狂乱になるわ」
「そんなことは無いと思うけれど」
また風が強くなった。
賑やかな打楽器と化した窓枠は、目茶苦茶なリズムを響かせる。
「私は・・・生きていける」
恐れおののきながら。
それでもまだ、絶望はしていないのだから。
カッサンドラとディミータ。
彼女らが話しているのは、「あの日」のこと。
退く
退く
船の上で、戦のさなかで、常に彼は命令に忠実であった。
舵をとるならどんな嵐でも絶対に手を離すなと言われ、大嵐の航海に耐え抜いたことがあった。
剣を握るならどのような状況でも怯むなと言われれば、血塗れになろうと絶対に退かなかった。
ただ黙々と命令を遂行していく彼に気を留める者などおらず、
舵に手を掛けてじっと海を見つめている彼の姿は風景のようなものだった。
「お前の意思を確認したい」
ある日、上官は唐突に切り出した。
新規編成部隊からの要請で、操舵手が欲しいというのだ。
ある程度の経験と、できればそれなりの戦闘能力があれば好ましいということだった。
それならばと、この上官が思い浮かべたのが彼だったというだけのこと。
「異動の話がある」
「かまいません」
彼は即答し、上官はふっとため息を吐いた。
「正直なところ、俺にはお前がわからない。
舵取りの腕も悪くない、戦闘能力だって高い。これは客観的な事実だ。
忠実な部下のお前はいったい何を考えてここにいるんだろうな」
「美しい、この海のことを」
「は?」
上官は眉を顰めて彼を見た。
彼はただ、その整った顔立ちに僅かな笑みを刻んで海に視線を巡らせた。
「海が見たかったのです。海で生きていけるのなら、それでいいのです」
そして彼は、ある日突然ギルバート部隊へとやってきた。
領海侵犯の異国船との小競り合いは、既に三日目をむかえている。
ヴィクトリアを追い詰める敵兵に目を止め、
その戦闘服の隙間を狙って差し込んだ剣は、寸分の狂いなく軟な肉体を突き刺した。
薙ぎ払ってしまえばそれでしまいだ。
しかし、戦闘服が邪魔でうまく剣を捌くことができない。
「マキャヴィティ!」
ヴィクトリアの叫び声でマキャヴィティははっとしたように振り向いた。
目の前の相手に気を取られていたマキャヴィティは、背後からの敵に気づくのが僅かに遅れたのだ。
振り向いた先には剣を振りかぶった敵兵の姿。
避ければヴィクトリアが危険に晒される可能性のある位置だ。
相手の身体から剣を引き抜いていては切られてしまう。
長年の戦闘経験から、相手の武器がどこにでもあるような剣だということを瞬時に判断して
マキャヴィティは左の手を構えて、籠手で振り下ろされた剣を受け止める。
重く鈍い音がしたのとほぼ同時に、
マキャヴィティは振り返りもせず剣が刺さったままの敵兵の身体を蹴り飛ばし
引き抜いた剣を振り上げざまに切りかかってきた敵兵の喉元を逆に切り裂いた。
真っ赤で温かな液体を浴びながら息を吐いたマキャヴィティは、左手に走る疼痛に顔を顰めた。
「ありがとうマキャ。剣を手で受けるなんて、大丈夫なの?」
「大丈夫だろう、たぶんな」
不思議な答え方にヴィクトリアが眉を曇らせてマキャヴィティの左手に手を掛けた。
その瞬間、マキャヴィティは激しい痛みに小さく呻いた。
「マキャ」
「問題ない。ただの骨折だろう。あの男を片付ける、それが俺の仕事だ」
マキャヴィティの視線の先には、自らも剣を振るいながら周りに指示を出している兵がいる。
身なりからしても、周りの兵たちよりは少々位が高そうだ。
「一個中隊の隊長クラスだ。あれを片付ければかなり相手は崩れる」
「それはわかるけど、その怪我では無理だわ」
「右の手は使える。それにこれは隊長命令だ」
痛みに時折歯を食いしばりながら、それでもマキャヴィティは全く退く気がなかった。
うまくいけば邪魔されずに相手に詰め寄れる位置なのだ。
命令を絶対のものとしているマキャヴィティには、命令遂行の絶好の機会だ。
「ダメよ、いくら命令でも今のあなたにどれだけ勝ち目があるの?」
「奴の腕はそこそこってレベルだ。大したことはない」
「それはマキャが万全のコンディションだったらの話でしょう?」
声は潜めても、ヴィクトリアは苛立っていた。
マキャヴィティの持っている剣は、本来片手で扱うようなものではない。
ヴィクトリアも今まで何度もマキャヴィティが剣を振るうところを見て、
相手の武器ごと粉砕するほどの威力があるほど重い剣だということを知っている。
それを片手で振り回すのは、いかにマキャヴィティの力が強いと言っても
正確に相手を斬るのは難しくなる上に手を痛めてしまうことにもなりかねない。
「今なら退くこともできるわ。私たちの船まで敵兵はほとんどいない」
「行くと言っている。これは命令なんだ!」
「命より優先する命令なんて無いわ。
マキャ、今出ていくことはあなたにとってとても危険なことなの。
それこそ命がけになってしまう。こんなつまらない小競り合いで命なんて懸けないで!」
戦闘服の帯をぎゅっと握って己を引き戻そうとするヴィクトリアを見下ろして、
マキャヴィティは不愉快そうに眉間に皺を寄せた。
「命を懸けるつもりはない。だが、結果的にそうなったとしてもそれが戦闘というものだ」
「でも!普通なら勝てる相手なんでしょう?どうしても行かなければならないなら私が行くわ」
「馬鹿な、俺でこそ勝てる相手でもヴィクトリアには無理だ」
「だったら一緒に退きましょう。ねえ、その手ではまともに剣も扱えないでしう?」
必死になって止めるヴィクトリアから目を逸らし、
マキャヴィティは標的にしている敵兵を見やった。
ほとんど隙のない身のこなしは、
確かに今のマキャヴィティが相手をするには少々厳しいものがある。
左手の痛みはかなり酷い。
それでもマキャヴィティは退くことを躊躇った。
敵に背を見せるのが嫌だとか、途中で退くことをプライドが邪魔するのだとか、
そういうわけではない。
ただ、命令に背くことになる。
「…隊長は、許してくれるだろうか」
「何言ってるの?その怪我で無茶する方が怒られるわ」
「そうか」
そうだった、とマキャヴィティは胸の内で呟いた。
ギルバートという男は、危ないと思ったら逃げろと平気で口にできる上官なのだ。
彼自身、勇猛果敢だけれども身の危険を感じたらさっと手を引く。
部下たちには、最低限自分の命を守れるだけの戦闘力を身につけろと言っては
相当量の訓練を課す。
そのおかげか、ギルバート直属の部下たちは部隊編成以降ひとりも欠けていない。
今マキャヴィティが怪我を押して危険な戦いに挑むことをギルバートはよしとしない筈だ。
「退こう」
呟いたマキャヴィティにヴィクトリアは頷いた。
「走れる?」
「随分手に響くが、歩いていくわけにはいかないだろう」
マキャヴィティは、手にしていた大剣を器用に背負った鞘に戻すと、
腰に佩いていた軍支給の片手剣を抜いた。
「ヴィクトリア、先に立って走れ。俺は後ろにつく。
気を付けるのは向こうのマストのマストの陰くらいだろう」
「わかったわ。戻ったらすぐに手当てするから我慢して付いてきてね」
そういうと、ヴィクトリアはほとんど音を立てずに走り出した。
なるべく左手を動かさないようにしながらマキャヴィティがそれに続く。
自分たちの船の方に向かえば敵兵はもういない。
梯子を渡した位置まで近づくと、不意に自分たちの船からタンブルブルータスが出てきた。
戦闘服の間から白い包帯が見えている。
「マキャ、もう終わったのか?」
「いや、ちょっと」
言葉を濁したマキャヴィティの視線を追って彼の腕を見たタンブルブルータスは、
わかったというように一つ頷いた。
「ディミが戻っている、手当てしてもらうといい。優しい治療は期待できないけどな」
「だろうな」
タントミールかジェミマがいれば、なるべく痛まないように治療してくれるだろう。
しかし、ディミータは手早く的確な治療がモットーだから患者には決して優しくない。
あのギルバートが治療を受けて涙目になっているところをマキャヴィティは見かけたことがある。
「お前が怪我で戻ってくるなんてな。まあ、ヴィクトリアに懇願されて戻ってきたんだろうけど」
「よくわかっているわね、タンブル。散々渋られたのよ」
「そんなことだと思った。せいぜいディミに泣かせてもらうといい」
そういうと、タンブルブルータスは真剣な顔つきに戻って敵兵の方へと走って行った。
「あなたが怪我しても退かないことを心配しているのは私だけじゃなかったのね。
さあ、治療に行って。私はまた行かなきゃいけないから。持ち場に戻るわ」
「ちょっと待ってくれヴィク。戻るときは一緒に俺も戻る、だから一緒に来てくれ。
正直言うと心配なんだ、ヴィクをひとりで行かせるのは。だから」
「そう言われても仕方ないわね、さっきも助けてもらったし。
わかったわ、取りあえず一緒に行きましょう」
ヴィクトリアが先に梯子を渡り、
マキャヴィティも危なげなくそこを渡って自分たちの船に降り立った。
その瞬間、船室から誰かの悲鳴が聞こえてきた。
「今のってランペルか?」
「だと思う。ディミってば女の子にも容赦ないのね」
「何だろう、強い敵と遭った時とは違うこのぞくぞくする感じは」
マキャヴィティが小さく身震いすると、ヴィクトリアは苦笑した。
「覚悟はいいかしら?」
「もう退けないじゃないか」
口の端を引き攣らせたマキャヴィティは、そう言って唾を飲み込んだ。
右手に提げた剣を無意識のうちにぎゅっと握りしめて船室に続く階段を下りてゆく。
戦場では決して見られないそんな彼の姿を愛おしく見ながら、ヴィクトリアも続いた。
「俺は無事にここから出られるだろうか」
「大丈夫。マキャは強いもの」
「そうか」
ヴィクトリアの言葉に勇気づけられたのか、マキャヴィティの背筋が伸びた。
力なくだらりと伸ばされた左手は痛々しいけれど、
新たな恐怖に立ち向かう彼の背中は、ヴィクトリアにはとても逞しく見えていた。
マキャヴィティほどの猛者でも生唾を飲み込むくらい怖いらしいディミの治療。
マキャは優先順位が、命令>自分のコンディションのタイプ。
武器ではないから * new *
武器ではないから
自分たちの部隊に、あの大海賊を討伐する司令が下っていると知ったのは
もう十日ほど前のことだ。
正直なところ、ジェミマは大変に驚いた。
彼女がこれまでに経験したのは、さしたる手応えもない俄海賊か
不法操業の商船などとの小競り合い程度で、
近海に名を馳せる大物相手の戦を命じられるとは努々考えていなかったのだ。
既に隊長のギルバートや参謀のカーバケッティが何らかの手を打っているということだったが、
戦の経験豊富な隊員たちの間に走った緊張が、いやがおうにも若手隊員たちを不安にさせた。
その日から、日々の鍛錬は厳しさを増した。
普段からギルバートの訓練はハードなのだが、
それでも手加減していたのだと全員が思い知った。
船の女性隊員はほとんど戦闘員としては役に立たないことをギルバートはわかっていて、
それでも自分の身くらいは護れるようにしようということなのか、
徹底的に相手の攻撃を受け流す練習をさせられた。
無論、攻撃のための訓練も行われたが、剣の扱いに慣れているランペルティーザを除いて、
女性隊員は限られた時間内でさしたる戦力になれる気配は無かった。
夜明けの甲板で、欄干にもたれ掛かったジェミマはぼんやりと仄明るい水平線を眺めていた。
いつも明るい彼女の目が僅かに曇っているのは、
昨夜起きた海賊との小競り合いの疲れからではない。
当然、寝ていない身体は疲れ切っていたけれど、それならば寝てしまえばいいだけだ。
「ジェミマ、眠れなくても横になって休む方がいいですよ」
気配を感じさせず、声だけが背後から飛んできてジェミマは思わずびくりとした。
「隊長・・・」
「眠れませんか?コリコなんかは、戦闘の後は興奮して眠れないと言いますが、貴女も?」
ジェミマの隣に立って穏やかに微笑むギルバートからは、戦の匂いがまるでしない。
制服の下には包帯が隠れているのかもしれないが、既に身体は清められて汚れすらない。
「興奮するほどのことはしていませんから。ただ、海を見ていたかっただけです」
「そうですか。僕はまた、貴女が落ち込んでいるのではないかと思ったのですが」
訝しがるような顔をしたジェミマに、ギルバートは小さく首を傾げた。
自分で言えということなのか、小柄な隊長は読めない表情で口許だけ笑みを浮かべている。
部下の悩み事を解決するのは隊長の仕事だとでも思っているのか、
ギルバートは何だかんだと隊員たちの心の内に入り込んでくる。
それが不快でないのがいけないのだとジェミマは小さく溜め息を吐いた。
彼には話してしまうのだ、時には秘めておきたいと思ったことでさえも。
「あたしって戦闘ではまるで役立たずだって思い知って」
「なるほど、それで?」
「でも、あんな風に否定されるのは納得がいかない」
「そうですか」
欄干に乗せていた手をぎゅっと握るジェミマの様子をちらりと見て、
ギルバートは少し考えてから口を開いた。
「まず一つ目について言うと、それは間違いですね。
ジェミマは戦闘中に怪我をした僕らの応急手当をしてくれましたし、
あの海賊たちを捕縛した後もみんなの身体を案じて働いてくれました」
「それは」
「あなたの仕事だからそうしたと言うのでしょう?
それで何か問題がありますか?僕は役目だから戦闘の指揮をしたまでです。
タンブルやランパス、マキャは戦闘を想定して配置されているので戦う義務があるのです」
その分の給金は支払われているのです、とギルバートは真面目に付け足した。
「戦場から逃げることは許されないのですね」
ジェミマが呟くと、小柄な隊長はくすくすと笑った。
「彼らは逃げるくらいなら死んだ方がマシだというくらいのプライドを持っています。戦士ですから。
でも、ジェミマはそれじゃいけない。貴女の役目は癒し手として戦士の命を守ることです。
それでは不満ですか?剣を執って戦いたい?」
「そういうわけでは・・・」
「厭でも剣を手にしなければならない時もあるかもしれませんけどね」
「それが」
呻くようなジェミマの声に、どうしたのかとギルバートは僅かに目を見開いた。
握っていた拳をもっときつく握りしめて、
どうにか声が震えないことを願いながらジェミマは続けた。
「それが、昨日だったんです。あたしはランペルがあいつらにやられるのを見てられなくて」
「咄嗟に剣を取ろうとしたわけですね」
いつもと様子が違うジェミマに気付いたギルバートは、
隊員たちにそれとなく訊ねて何が起きていたのか大体のことを把握していた。
捕縛命令が下っていた海賊に出くわし、事前の通達と調査から力押しで問題ないと判断して、
宵の口から数時間掛けて海賊船に追いつき戦に持ち込んで夜明け前には頭領を捕縛できた。
たいしたことのない、いつも通りの戦だった。
その戦の中で、ジェミマもやはりいつも通り後方で負傷者の手当にあたっていた。
衛生兵のタントミールと共に、休息がてら戻ってくる戦闘員たちの傷を清めて包帯を巻いた。
ボンバルリーナやディミータは武器の補充に走り、カッサンドラやヴィクトリアは見張りに立った。
そしてランペルティーザは武器を取って海賊に向かって行った。
彼女は元々海賊だったという経歴の持ち主で、
力は男性に到底及ばなくとも巧みな太刀筋で戦闘員をフォローすることができる。
「ランペルが脚を取られて転んだのが見えたんです。
そこにあの男が剣を振り下ろそうとして、すぐそこだったけど剣じゃ間に合わないと思って」
「確かに、その目測は誤っていないでしょうね。膝をついた体勢からでは特に。
投擲できる武器があればそれを使おうとするのは自然です」
「だからあたしは、これを」
半ば無意識にジェミマが腰の後ろ側に手を回すと、その手によく馴染む木の柄に触れた。
調理担当の彼女にとっては最も大切な仕事道具である包丁がそこに提げられている。
市場を探し回って手に入れた四つの包丁を自在に操って隊員たちの腹を満たし、
時には大道芸よろしくジャグリングを披露して場を涌かすこともある。
武器ではないが、いつも丁寧に手入れをしていて切れ味は鋭い。
「投げようとしたんです」
俯いて告げたジェミマに、ギルバートは微苦笑を向けた。
「僕がもしそんな貴女を見ていたら、やっぱり止めたと思います。
ランパスはちょっと、やり方が乱暴なので貴女を傷つけてしまったようですが」
「・・・あたしには無理だからですか?」
咄嗟に包丁を抜いて振りかぶったジェミマを、
ちょうど武器を換えに戻っていたランパスキャットが
後ろに突き飛ばすようにした所為で彼女は体勢を崩して転ばされた。
しかも「止めろ、莫迦」という罵倒付きで。
「正直なところ、それもあります。投擲用の武器を扱うのは大変難しいのです。
変に回転したり軌道が捩れたりするので、技が未熟なら味方を傷つける可能性も高い。
貴女はトスは得意ですが、スローは訓練していないでしょう?」
「・・・したことは、ないです」
「まあ彼も莫迦という必要はなかったのですが、口が悪いので大目に見て上げて下さい。
それと、止めた理由はもう一つ。こっちの方が大きいと思います」
ジェミマは伏せていた顔をそろりと上げてギルバートに目を向けた。
相変わらず彼の口許には微笑が浮かんでいる。
「その包丁は武器ではありません。僕らを心から楽しませてくれる、貴女の仕事道具です。
もしもそれで誰かを傷つけた時、それは殺傷力を持った武器になってしまいます。
そして貴女はたぶん、それをずっと悔いるし、それで料理ができなくなる」
「それは・・・そうかもしれませんが」
「僕はそんな風にして大切なものを失っていった者たちをたくさん見てきました。
今の貴女には実感できないかもしれませんが、僕はそれで誰かを傷つけて欲しくはない。
今回も、投げるなら剣の鞘でも何でも良かったのです。相手を怯ませられればそれで」
少しの隙ができれば良かったのだと指摘され、ジェミマはきゅっと唇を噛んだ。
そういう咄嗟の判断がまだ彼女にはできない。
助けなければという思いだけが先行して冷静に状況が読めていなかったのだ。
現に、あの後ランパスキャットは短剣の鞘をあの男に投げつけていたのではなかったか。
「すみません、あたし全然そういうこと考えられなくて」
「何事も経験ですからね。あと、本気で投擲武器を扱いたいなら教えますよ。
僕もうまくはないですが、基本的なことなら知っていますから」
にこにこと笑うギルバートは、どこかわくわくとした雰囲気を醸し出している。
それに戸惑いつつも、ジェミマには断る必要の無い話だったので一つ頷いた。
「そうですか!ナイフもいいですけど、アックスなども格好いいですよね。
手裏剣とか、スリングショットなんかもユニークで良いかもしれません」
「半分以上わからないんですけど」
何故こうも男性陣は武器の話となるとこれほどキラキラと目を輝かすのだろうか。
そう言って溜め息を吐いていたのは誰だっただろう。
「それはそれとして。とにかく貴女は否定されたのではなく心配されたんですよ。
彼はさっきディミに小言を食らっていたのでそれで勘弁してあげてください。
余計な一言付きで突き飛ばすなんて、ジェミマも腕を擦りむいたのでは?」
「ほんの少し。でも、心配してくれてのことなんだから平気です。
あ、そろそろご飯用意しなきゃ。美味しいの作りますね」
欄干から身体を離し、ジェミマはいつもの明るい笑顔を見せた。
「期待していますよ。でも、休まなくて良いのですか?」
「大丈夫です、気持ちが復活したので元気なりましたから。
今日はレモンの蜂蜜漬けも出しますね」
跳ねるように船室へと消えていくジェミマの後ろ姿を見送って、
ギルバートは小さく安堵の息を吐いた。
そして、誰かが背後に立つ気配を捕らえてゆるりと振り返る。
「いつまでも殺生を知らない無邪気さを守れるなんて思っていませんよ。
でも、彼女が僕らに与えてくれるものの暖かさを思えば、守れるだけ守りたいのです」
「俺は何も言ってませんよ」
じとりと見下ろしてくる目線を綺麗にやり過ごし、
ギルバートは近くに置いてある木箱の上に飛び乗った。
逆に相手を見下ろしてフンと鼻を鳴らす。
「言って無くても貴男の表情が雄弁に物語っているのですよ、カーバ。アンタは甘い、とね」
「自覚があるならけっこうです。それよりも、グロールタイガーの件で話を」
「わかりましたよ。本当に、海賊というのは厄介ですね」
戦で疲れの残る身体を伸ばして、ギルバートは船室に向かうカーバケッティの背を追った。
立ち止まって悩んでいる暇は無い。小さな失敗を嘆いている時間も無い。
ギルバートにも、隊員たちにも。
決戦は日一日と迫ってきているのだから。
隊長は部下の悩み相談から暴言の始末まで何でもこなします。
ジェミマの武器は普通の剣、包丁はあくまで仕事道具。
これが第一章の直前くらい。