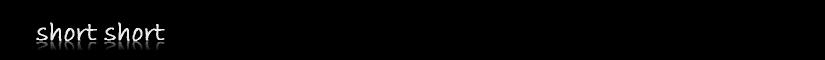キャラメル色の
キャラメル色の
柔らかなストールを手に、カーバケッティは町外れの劇場にやってきた。
今日は休演なのか辺りは静かだった。
「ガス、いるか?」
慣れた足取りで裏口に回ったカーバケッティは、ひょいと中をのぞき込んだ。
幔幕の向こうは薄暗く少し埃っぽい。
「何か用か?」
裏口のすぐ近くで嗄れた声がして、おんぼろの毛玉がのそりと動いた。
カーバケッティはするりと中に入って老いた猫の傍に座った。
「ご無沙汰だったな」
「時々来てたんだけどな。けっこう行き違いが多くてさ」
「そりゃ悪かったな」
ガスはそう言って身体を起こした。
その腹の下にあるブランケットを見てカーバケッティは僅かに目を見開いた。
「新しくなったのか。ジェリーか?」
「持ってきたのはあの子だが、誰かからの差し入れだとかいう話だ」
「へえ。ガスのファンだったのか?」
そうらしいな、と呟いた老いた猫が嬉しそうに目を細める。
ガスはかつて人気俳優だったのだとカーバケッティは改めて思い出した。
その頃の面影は既に無いが、カーバケッティの記憶の中では凛々しい二枚目俳優が豪快に笑っている。
「それでお前さんは何の用だ?」
「ああ、これをな。渡そうと思って。そろそろ冷えるようになってきたし」
「ほう」
カーバケッティが広げてみせたストールをガスは目を細めて見つめる。
入り口の幕は開いたままで、爽やかな光が幔幕にさしこんでいるのだから
ガスの目でも広げられた羽織ものの繊細なできはよく見えていた。
「貰ってくれたら嬉しいんだけど」
「彼女はいいのか?」
「これはガスに渡したいものだから」
暖かなキャラメル色に濃褐色で模様が入ったストールをガスの肩から掛けて
カーバケッティは満足そうに微笑んだ。
「似合うと思うよ、ガスおじさん」
「お前さんのおじさんになった記憶はないが」
「まあまあ、暖かいだろう?」
そうだなとガスは呟いた。
年を重ねるほど寒さは身に堪えるようになっている。
何も言わなくても、ガスの身体を案じる若者が街にはたくさんいる。
「相変わらず器用だな」
「ジェリーやカッサと張れるかな」
「そこそこ良い勝負はできるだろうよ。ありがたくもらっておこう。礼を言う」
ガスと目が合ったカーバケッティが照れたように微苦笑を浮かべる。
「他に必要なもんとかあったら言ってくれ。まあジェリーがいるから大丈夫と思うけど」
「そんなに俺を気遣う必要は無い。年寄り相手じゃ退屈するばかりだぞ」
「ガスの話はけっこう好きだぞ。バストファさんの話よか断絶おもしろいしな」
「調子の良い奴だ、こないだは寝ていたように見えたが」
決まり悪そうに首をすくめたカーバケッティは、踊った後で疲れていたのだと言い訳をする。
「かまわんよ。こうして来てくれるだけでかまわないんだ。酒の相手をしてくれりゃあもっといいが」
「いつでも飲むぞ、俺はそこそこいけるクチだからさ。
ほんとに、ガスから貰ったものはこんなストール一枚じゃ全然返せないから」
「俺は何もしとらん」
「じゃあ俺が一方的に感謝しとく」
大雪に降られて餌が全く無く空腹を抱えて動けなかった時も、
街が無秩序に乱れて怯えながら生きていた時も、
ガスはいつも豪快に笑いながら旅公演のお土産と食べ物を気前よく皆にわけてくれた。
それは、幼いカーバケッティにとって命と安らぎを貰ったに等しかった。
だからカーバケッティはガスのところに来ては取り留めのない世間話などをしていく。
やせ細っていた幼子はこんなに大きくなったのだと老いた猫に伝えるために。
「ガス、今日は天気が良いからちょっと散歩しないか?」
「そうだな、行こう」
ゆっくりと立ち上がるガスにさり気なく手を貸して、カーバケッティは訊ねる。
「負ぶわなくて大丈夫か?」
「年寄りをあまりバカにするもんじゃない」
それに、と言いながらガスは先に立って幔幕の外に出て行く。
後に付いて出たカーバケッティが老いた猫に並んで立つと、劇場猫は緩やかな笑みを浮かべた。
「それは俺の台詞だったはずだがな」
「はは、覚えてたんだ?」
「お前さんはおとなしい子供だったが負けん気は強かったからな。
負われるほど子どもじゃないって言い張ってなあ」
何度転んでも、どんなに疲れても決して弱音は吐かなかったカーバケッティにガスは舌を巻いていたものだ。
「根性があるから良い役者になれると思ったんだが」
「あまり打たれ強くはないんだ。しごかれたら落ち込んでしまう」
「よく言う」
ガスとカーバケッティは穏やかに笑いあいながらのんびりと歩いてゆく。
かつてガスが幼子に合わせてゆっくりと歩んだように、今はカーバケッティが老いた猫に合わせて歩む。
「どこに行く?」
「今日は土手を歩きたい」
「了解」
幽かな風を受けて、カーバケッティは昔よく転んだ道を、老いた猫が転ばないよう注意を払いながら進む。
「ここはあまり変わらないな」
「そうだな」
「静かだし良い場所だ。お前さんも俺なんかじゃなくて彼女をおぶって散歩すりゃいいじゃないか」
「いやいや」
カーバケッティは苦笑して遠い目になった。
「彼女にそんなことを言った日には、俺はガスを送る前に霊界空港に行っちまう」
「なる程、今の言葉をディミータに聞かせてやりたいものだ」
「ちょっと、勘弁してくれよ」
情けない表情の青年を見やってガスは愉快そうに笑った。
「お前さんは随分打たれ強いさ、何せディミータと渡り合えるんだからな。
役者になりたくなったらいつでも来い、稽古を付けてやる」
「いやあ、俺には華がないからなあ」
「何を言う。お前さんは充分にスマートじゃないか」
「さすが名優、口達者なことで」
やはり苦笑で受け流しながらも、カーバケッティは滅多に言われないほめ言葉を喜んでいた。
微風にキャラメル色のストールが揺れるのを見ながらガスを支えるようにさり気なく寄り添うと、
気付いたらしいガスは何も言わずに笑みを浮かべたまま歩いてゆく。
「良い天気だな」
「本当にな」
また少し、暖かな色のストールが揺れて風が土手を渡ってゆく。
舞台上でガスに話しかけるカーバケッティを観て書いてみたもの。
うちのカーバは街の古参組なのでガスとの付き合いも結構長いわけです。
彼の若い頃を知っていて、彼に色々助けて貰ったことを感謝もしているのです。