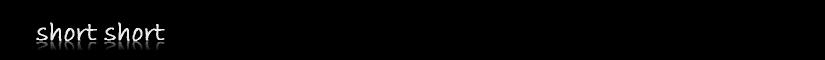名付けられない色
名付けられない色
暖かな日差し、緩やかな風。
凍えるような寒さは去って、冬は終わりを迎えようとしている。
それでもまだ冷たい風から愛おしい者を守るために、
タンブルブルータスは小さな女性を包み込むように丸くなっていた。
伝わってくる温もりと規則正しい鼓動は、彼にとって安らぎそのものだった。
ここに忍び寄っている気配に敵意があれば、彼はすぐに飛び起きただろう。
しかし、そうではない。
そうであれば彼がこの安らぎから離れる必要はどこにもなかった。
「やあ、タンブル。日向ぼっこ?寒くないのかい?」
限りなく無声音に近い声なのに、声色はただただ陽気だった。
目を閉じていたタンブルブルータスが眠っていないことをあっさり看破した
このあなどれない訪問者はマジシャンのミストフェリーズ。
タンブルブルータスは薄く目を開けてちらりと黒猫を見た。
「これ以上ないくらい温かいが」
「ああ、そうだね。無意味で無粋な質問だったよ」
肩をすくめたミストフェリーズは、タンブルブルータスの傍に腰を下ろした。
「何をしに来た」
「散歩だよ、ちょっと春探しにね。大丈夫、カッサを盗ったりはしないよ」
「ふうん」
興味の欠片もなさそうなタンブルブルータスの態度に気を悪くするでもなく、
マジシャン猫は足許に咲いている小さな花に視線を投げた。
「こういう花だって春だと思うんだけど。少し暖かくなったからね。
キレイな色をしているよね。何ていう色なんだろう」
ピンク色のようでもあり、紫色のようでもある。
春にふさわしいパステル色の花は、微かな風にも儚げに揺れている。
「必要なのか、色の名前など」
「知っていても困らないしね。こういう花があって、どんな色でって
誰かに話したいときには知っていると伝えやすいよ」
それに、と言ってミストフェリーズはにっと笑った。
「名前というのは術をかけるための重要な要素なんだよ。
だから、僕は名前を知りたいと思うのかもね」
「複雑なんだな」
「全然複雑な話じゃなかったよね?」
ミストフェリーズは苦笑する。
この無愛想な男から合いの手が入るだけでよしとしなければならない。
そのタンブルブルータスは、抱いた女性に愛おしげな目を向けている。
「本当に仲が良いんだね」
「俺にとっては」
感心したような黒猫の言葉に答えたわけではないだろうが、
タンブルブルータスは低い声で呟くように話し出した。
「やはり、色の名前など必要が無い」
「どうしてさ」
「俺はカッサンドラの目の色をよく知っている。
だが、その色が何という色なのかは知らない」
僅かに口許を弛めて、タンブルブルータスは目を閉じた。
その穏やかな表情が珍しくて、ミストフェリーズは僅かに目を見張った。
「色に付ける名を知らなくても、俺はその色を心底美しいと感じられる。
充分だ、それ以上俺には必要ない」
「君らしいね」
寄り添った二匹の猫たちからの返事はない。
ミストフェリーズは小さな花に目を落とした。
「色の名前は要らない、か。それもいいかもしれないなあ。
一度君の色に名前を付けてしまったら、君はその色でしかなくなるしね」
花の色も瞳の色も、光の加減一つで全く違った色に見えるのだから。
気の早い小さな春にそっと触れて、ミストフェリーズは微笑みを浮かべた。
「彼らには敵わないよ。僕もいつか、あんな風に思ったりするのかな」
名付けられない色でゆらゆらと揺られる花は、それでも確かに可憐で美しい。
春はもう、すぐそこに来ている。
タンブルブルータスとミストフェリーズ。
花の色も花の名前もタンブルブルータスには関係はない。
黄色い花も紫の花も、たぶん口で言ったって本当の色は伝えられない。
失って 手に入れて
失って 手に入れて
柔らかな春の陽光。
幽かに花の香りのするそよ風。
心地よさに微睡んでいたヴィクトリアは、名前を呼ばれて薄く目を開けた。
「ヴィクトリア?ああ、すまない。寝ていたか?」
「いいえ、うとうとしていただけよ」
暖かな平屋の屋根の上に丸くなっているヴィクトリアを、
石の塀に立って見上げているのはマンかストラップ。
見事なシルバータビーを纏い、頑丈そうな四肢で立派な体躯を支える街の若いリーダーは
いつもの明るい表情ではなく僅かに眉間に皺を寄せていた。
その理由が何となくわかったヴィクトリアは僅かに笑みを浮かべて言う。
「マンゴとランペルなら見ていないわ」
「そうか、相変わらずすばしっこい奴らだ」
目を吊り上げたマンカストラップだが、ふと気付いたように真顔に戻った。
「俺はマンゴたちを探しているとまだ言っていなかったように思うが」
「あら、みんなわかるんじゃない?貴方にそんな顔をさせるのは彼らくらいよ」
「まいったな、そんなに変な顔をしていたか?」
ぐりぐりと顔を撫でるマンカストラップが愛おしくて、ヴィクトリアは小さく笑った。
「変な顔じゃなくて頑張ってリーダーであろうとしている顔よ。
マンゴとランペルのやっていることをやめさせないと、と思いながら
どこかで彼らの輝きを誇りに感じているような、そんなリーダーの顔かしら」
「そうなのか。俺は自覚が無いが、ヴィクトリアがそう言うならそうなのかもしれないな」
「あら、私は随分信用されているのね」
勿論、と微笑むマンカストラップの首には黒に銀の鋲飾りの首輪がある。
毛艶の良いマンカストラップのことだから、人間たちには飼い猫に見えるだろう。
「邪魔して悪かった。それじゃ俺はもうちょっと奴らを探すことにするよ」
「そう、わかったわ。ねえマンカス、行く前に一つ聞いていいかしら」
「かまわない、どうかしたか?」
行きかけていた身体を反転させたリーダー猫は、何事かとヴィクトリアを見やる。
「疑問に思ったの。マンカスはどうして野良になったのかしらって」
「ヴィクは野良になったことを後悔しているのか?」
「いいえ、今は全く」
マンカストラップは少しばかり迷っていたようだが、やがて苦笑を浮かべた。
「俺は飼われていた頃が良かったと微塵も思ったことがない。
野良になって得るものもあれば失うものもあると皆言うが、俺には失ったものがない。
可愛がって貰った記憶は無いし、暖かい寝床とうまい飯なら今の方が断然上さ」
「ならば今は幸せ?」
「そうだな。ヴィクトリアはどうだ?」
問われたヴィクトリアは、記憶を辿った。
何不自由なく、暖かい部屋の柔らかな寝床と栄養あるご飯が食べられた日々。
自分を抱き上げるヒトの声とピアノの音。
「あのまま飼われていたら今とは別の幸せがあったかもしれない。
でも、あのままでは見つけられなかった喜びが今はあるから」
「そういうものなんだろう。正しかったとか、間違っていたとかそういうのではないんだ。
その時一番正しいと思ったものを選択しながら生きてきた、その結果が今だ」
「そうね。私たちはいつも選択をして、何かを得て何かを失っているのかもしれないわ。
ありがとうマンカス。引き留めてごめんなさい」
「いや、良い一日を。ヴィクトリア」
春の日差しのような暖かな笑みを残して、リーダー猫は颯爽と走ってゆく。
直後、ヴィクトリアの目の前に二つの影が落ちてきた。
「やあ、ヴィク」
「今日は気持ちいいわね!」
追われている緊張感などまるでない泥棒猫たちだ。
「なるほどなるほど、一番正しい選択をすることが大切なわけだ」
「何がなるほどなのよ」
「ほら、今日の獲物は多すぎて重いから下手すると捕まるだろ?
だから、本当に必要なモノ以外は捨てるべきだと思ってさ」
呆然としているヴィクトリアの前で、泥棒猫たちは収穫物を広げ始めた。
他愛ないモノばかり、ヒトにしてみればがらくたのような物もたくさんある。
ランペルティーザはたくさんの獲物の中から、薄青のガラスのリングを拾い上げた。
「ほら、キレイでしょ?あげるわ。これヴィクの目の色に似てるの」
「あ、ホントだ」
ひょいとのぞき込んだマンゴジェリーがリングとヴィクトリアを交互に見て呟く。
呆気にとられた顔のヴィクトリアの手にリングを握らせて
ランペルティーザは嬉しそうな笑顔になった。
「やっぱり似合う!」
「そ、そう?」
「うん」
「おー、ぴったりの色だな」
マンゴジェリーも嬉しそうに笑う。
笑った泥棒猫たちはよく似ている。
要らない物はあっさりと捨てて、いる物だけを袋に詰め直す手際の良さに
呆れよりも感心を覚えながらヴィクトリアは泥棒猫たちを見ていた。
「ランペル」
「何?」
「ありがとう」
きょとんとしたランペルティーザは、すぐに合点がいったように頷いた。
「いいのいいの、それはヴィクにあげたいって思ってたんだから」
底抜けに明るいランペルティーザの笑顔がヴィクトリアは本当に好きだった。
幼い日、この黄色くて小さな虎猫に連れられて家を出たあの日。
ヴィクトリアはたくさんの物を失った。
暖かな寝床。
探さなくても用意される食べ物。
飼い主の温もり。
そこにあったはずの、未来。
そしてその日から、ヴィクトリアはたくさんのものを手に入れた。
それは今、彼女の周りにある全て。
マンカストラップは幼少時代は人に飼われていました。
その頃は彼にとって苦痛でこそあれ、幸せではなかったようです。
ヴィクトリアはランペルティーザに連れ出されましたが、
マンカストラップはラム・タム・タガーに連れ出されたのです。うちでは。