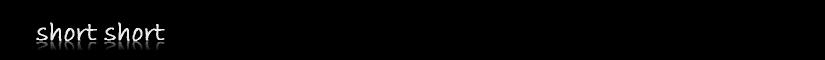いなくなったとしても
いなくなったとしても
雨上がりの教会の庭で二匹の猫が騒いでいる。
教会の人間たちは気付いていないのか気にしていないのか、
邪魔が入らないまま既に半時ほどが経過していた。
辺りは時を追うごとに明るくなり小鳥も鳴き交わし始めたが、
こんなところで大きい猫二匹が唸っている所為か鳥の姿は見えない。
「よく飽きないよね」
途切れることのない喧噪を聞くともなしに聞きながら
近くの木の枝に身体を預けていたミストフェリーズは呟いた。
下で騒いでいるのはマンカストラップとラム・タム・タガーだ。
大本の原因は派手な色男の方だろうが、
縞のリーダー猫も重箱の隅を突くような細かいことを並べ立てるのだから
それが我慢できない天の邪鬼が火に油を注ぐようなことを言い、
さっきから諍いの勢いは衰えることを知らない。
「こりゃあまた遠慮会釈のない悪態で」
不意に黒猫の耳に随分間の抜けた声が入ってきた。
気配は感じていたから驚きも振り返ることもせず、
ミストフェリーズは近づいてきた影に向かって声を掛けた。
「マンゴ、こっちにこないでよ。枝が折れると大変だから」
「そんなやわじゃねえと思うけど」
まあいいかと呟きながら、赤毛の泥棒猫は一つ高い枝へと身軽に移った。
「何しに来たの?」
「特に用はない、ただの通りすがり」
「ふうん。興味本位ってやつだね」
「そうとも言うだろうな」
リーダーのマンカストラップも天の邪鬼のラム・タム・タガーも、
他の猫たちの前で子供みたいな喧嘩などまずすることはない。
それが、二匹になるとたちまち子供じみた喧嘩を始めるのだ。
時には取っ組み合いにすらなるという。
「たまにはこういうのも必要なのかな」
「こんだけ怒鳴っちまえばストレス発散になるだろうよ」
「僕なら余計ストレスになりそうだけど」
互いに遠慮無く本音をぶちまけて手まで出ても
それでもあの二匹は誰よりも信頼しあっているのだ。
「口では鬱陶しいと言ってるけど、結局は互いに必要な存在ってわけだね」
ミストフェリーズは溜息を吐いて、ようやくマンゴジェリーに目を向けた。
「マンゴは?泥棒ってストレス発散になるのかい?」
「ありゃあ寝て起きて食うのと同じレベルだ、生きてるって意味でさ。
むしゃくしゃする時は俺より先にランペルが喚いてくれる」
「一心同体って感じだね」
庭では未だに悪態の応酬が続いている。
未だ鳥の影は見えない。
ミストフェリーズは喧嘩に背を向けて、赤毛の猫とお喋りの体勢になった。
「でもさ、感情を任せられるほどランペルの存在がマンゴの中で大きいと、
もし・・・もしも、ランペルがいなくなったらマンゴはどうすんのさ」
「そうだな」
マンゴジェリーは苦笑にも似た僅かな笑みを口許に浮かべた。
「ランペルがいなくなっても俺は生きられるさ。
あいつがいないと生きられない、なんてことは言わない。
俺がいなくなっても、ランペルだって生きていくだろうし」
「そうだろうけどさ。でも、自分にとって大切なものが欠けるんだよ」
「それまでと同じように生きられるとは言ってない。
日常の一部にあるはずの存在を失ったら、それが大きいほどに
その後を生きることは喪失感と戸惑いだらけだろうな」
そこにいて何気ない言葉に応えてくれる相手がいない。
背中を預けていられる相棒がいない。
そんな日常が突然訪れてもすぐに慣れられるはずがない。
「一心同体のようだって言っても身体や魂は別々だからね。
どっちかがいなくなったからってもう一方もいなくなることはない。
けど、そういう近しい魂は時に呼応するんだよ。同じ世界にいなくても」
「あっちの世界に呼ばれるってか?まあ、それもいいんじゃねえの?
それに応えるかどうかは生きてる方が決めりゃあいいこったし。
しっかし不公平だな。あっちの世界からは呼べるのにこっちからは無理ってさ」
「いや、もともと向こうは魂の世界だからね。
魂が魂を呼ぶのはおかしくないけど、こっちに魂だけ呼ぶのも変でしょ?」
難しいことはわからねえ、とマンゴジェリーは肩を竦めた。
「とりあえず、どんだけ五月蠅くってもあいつらはあのままの方が良い。
どっちも俺にとっちゃ天敵みたいなもんだけどよ」
「マンゴが泥棒するからマンカスも怒るんだよ。
ランペルがタガーにきゃあきゃあ言うのは知ったことじゃないけど」
「ああ、それじゃあ俺が何かしでかす度にマンカスは思う存分怒れるってわけか。
俺もリーダー殿のストレス発散に役立ってるんじゃねえ?」
それはない、とミストフェリーズは言下に一蹴した。
「マンゴとランペルはマンカスにハゲを作る原因にはなれるだろうけどね」
「言うねえ。ミストとタガーの喧嘩だってマンカスの腹痛の原因だぜ」
「喧嘩?そんなんじゃないよ、そんな子供みたいなことはしないさ。
タガーがちょっかい掛けてくるから制裁食らわしてるだけだよ」
細かい違いはどうでもいいとマンゴジェリーは思うのだが、
黒猫にとってはプライドに関わるほどの違いがあるらしい。
「で、どうすんだ?あのまま続けてりゃあ人間に迷惑だろうが」
「マンゴの口からそんな言葉が聞けるなんて思わなかったよ」
皮肉を口にするのは習い性なのだろう。
ミストフェリーズは渋い顔のマンゴジェリーに、大丈夫だよと言った。
「マンカスとタガーが揃って怖がる男が帰ってきたら終わるよ。
ここに来る前に公園の向こうで会ったからそろそろ帰ってくるんじゃない?」
「おお、噂をすれば。あ、気付いたかな?」
「こんだけ騒いでたらちょっと向こうからでもわかるからね」
向こうの方で男が駆け出したのを見て、
ミストフェリーズとマンゴジェリーは心の中で十字を切った。
掴み合いに発展したマンカストラップとラム・タム・タガーは、
未だに濡れている教会の庭に転がって草と泥に塗れている。
体勢はややマンカストラップ有利だが、決着は付きそうもない。
駆けつけたタンブルブルータスの拳骨の制裁まであと少し。
タンブルブルータスとミストフェリーズ。
花の色も花の名前もタンブルブルータスには関係はない。
黄色い花も紫の花も、たぶん口で言ったって本当の色は伝えられない。
紳士にご褒美を
紳士にご褒美を
しとしとと降り続く雨は、夜になっても相変わらず街をぬらし続けていた。
不快指数は高いまま、身体は重くなる一方だ。
こうして降り続いた雨がいつか街を沈めるのではないかと、時折思う。
ただ、どんなに雨が降っても身体が沈むことすら無かった。
ジャンクの隙間にできたそこそこ広い空間で、様々な物を叩く雨の音を
聞くともなしに聞きながらカーバケッティはまた一つ寝返りを打った。
暗くて生ぬるいものが辺りを覆っているかのように、ひたすら重苦しい不快感が纏わりつく。
息をすることすら億劫だと思った刹那、俄かに気配が近付いてきた。
重い頭を持ち上げて、いつでも動ける体勢に変えようとしていると、不意に知った声が聞こえてきた。
「誰かいるわ」
アルト気味の落ち着く音に、カーバケッティは何故か大いに安堵した。
それに応える低い声はくぐもって聞こえにくい。誰だか見当は付いているが。
「カッサ?」
暫く出していなかった声はやはり喉が貼り付いたかのように不安定に揺れたが、相手までは届いたらしい。
「カーバ?お邪魔していいかしら」
「勿論」
雨に濡れないというだけの場所は、思いがけない相手と一緒に過ごす空間になった。
もぞもぞと奥に移動しようとすると、不意に呼び止められる。
振り向くとカッサンドラの身体がすぐ傍にあって、その向こうにはタンブルブルータスの身体があるようだ。
カッサンドラが振り返って何事か囁いているようだが、雨の音に紛れて聞こえはしない。
少しして、辛うじて「わかった」と低い声が耳に届いて、同時に声の主が静かに立ち去る気配がした。
「どこに行ったんだ?随分降っているだろう」
「用を思い出したのよ。タンブルが行ってくれるって」
「そうか。良い奴だな」
見え透いた嘘だろう。カッサンドラはこんな雨の中に大切な相手を遣いになど出すことは無い。
嘘とわかったなら騙されたフリをすること、それが幼い時からの暗黙の了解。
取って付けたような陳腐な理由は、その後にある大切な何かの前置きに過ぎない。
「久しぶりね」
「うん?」
「カーバとこうしてふたりになるのは久しぶりだと思って」
カッサンドラの優しい微笑みを見つめたまま暫く記憶を辿って、
彼女と一緒にいた目当ての記憶にはすぐ行き当たらずに結局頷いた。
「いつもそうしていた筈なのにな」
幼かった頃はいつもカッサンドラがいた。
面倒を見てくれたジェニエニドッツが出掛けてしまったときも、ずっと傍にいてくれた。
それが当たり前だったのに、いつの間にか言葉を交わすことすら少なくなった。
たぶんそれは互いにおとなになったからでなく、彼女の傍にいるべき男が現れたからだろう。
「気を遣わずにもっと頼ってほしいと思うのは私の我が儘かしら?」
「え?」
「怖い夢を見たり落ち込んだり、小さい貴方は不器用に隠そうとしていたわ。
私も子どもだったからどうしてあげればいいかわからなくて」
カッサンドラの手がそっと頭に触れてくる。小さくて華奢だけど、その感触は安心感そのものだった。
「こんなに大きくなっても貴方は不器用なままね。甘えるのだって下手なまま」
「不器用じゃないと思うけど。誰かに指摘されたこともないし」
「気付いているわ」
ニコリと笑って断定されれば反駁する気も無くなるというものだ。
「でも言わないの。言っちゃいけないかなとみんな思っているから」
「なんで」
「貴方は絶対に何でもない平気だって言うでしょう?周りに心配を掛けるなんていけないと思ってる」
間違っていない。だから小さく頷く。
「我慢を教えたのは私。でも、甘え方は教えてあげられなかったわ」
「充分甘えていたさ。カッサにも、おばさんにも。あとは性格だろう」
カーバケッティの口元にようやく笑みが浮かんだ。
目の前のカッサンドラは逆に眉を曇らせる。
「いいのよ、カーバ。私は知っているから。貴方は今とても不安定になっている」
「そんなことは…」
「今夜は雨だからちょっと冷えるし、ねえカーバ」
首筋にカッサンドラの小さな頭が触れる。
カーバケッティがカッサンドラより身体が小さかったのは記憶も曖昧なほど小さな頃だけで、
背丈などを意識し始めた時は既に彼女の目線は自分より下にあった。
「ずっと前みたいに一緒に眠りましょうか」
「や、それは」
「私や彼に気を遣うのはやめてね。私はただ、不安そうな貴方の傍にいたいだけ。
今になってもこんな風に頭を撫でてあげることしかできないけれど」
見上げてくる顔に苦笑が浮かぶ。
「何かあったの?」
「わからない。たぶん、これと言った原因は無い」
性格だろうか。
常に周りに気を配って、弱い者は見捨てられない。計算高いフリをしながらいざとなれば損は省みない。
ついでに言えば若干の悲観的思考の持ち主。
遠慮のない友に言われたことはどこかで自覚していた。
「どうでもいいことが取り留めなく不安になる。この雨が止まないんじゃないかとか」
「それはカーバ自身のSOSじゃないかしら。いつも周りばかり見るんじゃなくて、自分のことも気にしてねって。
不安な時だけは貴方も自分を意識するでしょう?自分は何が不安なんだろう、どうにかしないとと思わない?」
「そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。でも、こうして優しくされるのは案外嬉しい」
疲れていたのかもしれない。不安を口にしたかったのかもしれない。
弱音を吐いても許されると思ったからか、ついつい本音が口を突いて出た。
カッサンドラが嬉しそうに微笑んだ。
「カーバが嬉しいと私も嬉しいわ、本当よ」
「ああ、知ってるよ」
初めて木に登ったときも、初めて狩りをしたときも、嬉しそうに報告した自分の話を聞いて
カッサンドラは自分のことのように嬉しそうにほめてくれた。
「なあ、カッサ。正しい優しさを持った男の子になってねって、俺に言ったのを覚えてるか?」
「ええ、覚えているわ」
「俺、そうなりたいとずっと思ってた」
甘えさせることも叱ることも優しさで、何が正しいかなんてきっと誰にもわからない。
だから、いつか尋ねてみたかった。
「及第点?」
「そうね。貴方は街一番の紳士だと思うわ」
「そりゃあ何よりだ」
誰かに認められたくて優しさを求めたのではないけれど、彼女に褒められることは素直に嬉しかった。
かつて、カーバケッティの世間が長老猫とジェニエニドッツ、カッサンドラと彼自身だけで構成されていた頃は、
彼女に褒められることが世間の大半から認められることと同じ意味を持っていて、
その価値観が未だに脳の片隅に残っているからなのかもしれない。
「今夜はご褒美だと思うことにしよう」
「大袈裟だわ」
くすくすと笑うカッサンドラにつられ、声を立てて笑う。
相変わらず雨は降り続いていて身体は重いけれど、纏わり付いていた不安は薄れていた。
すぐ隣にある懐かしい温もりを感じながら、抗いがたい眠気に身を任せる。
「おやすみ、カーバ」
その声に応えたかどうかは定かでなく。
今宵配られる夢に思いを馳せるでもなく。
カーバケッテは静かに寝息を立て始めた。
カーバケッティはカッサンドラに淡い思いを抱いていて、
それは恋と呼べるようなものにはならなかったけれど、
やっぱりカッサンドラが傍にいてくれると嬉しくて安心できるのです。
何で子の二匹かって、昔のタイヤダンスのパートナーだからです。
合図
合図
雨上がりの街はいつも以上に匂いが濃い。
水の匂いと、水に濡れて蘇ったように活き活きとし始めた草木の匂い。
噎せ返るほど濃厚な命の匂が充満する夜明けの街を
コリコパットは毛並みが水滴で濡れるのも構わずに疾走していた。
少年と言って差し支えない華奢に見える体つきで
険しい表情であっても少女と見まごうくらいには整った顔立ちをしている。
いずれ、彼が成熟した雄猫でないことは間違いがなかった。
「止まれ」
不意に聞こえた低く鋭い声に、コリコパットは反射的に足を止めた。
金属製の側溝はよく滑って思うようには身体は止まらなかったが、
止まれと命じた雄猫にぶつかる前には何とか踏みとどまった。
「ここだな。感じるか?」
振り向かないままにコリコパットに問いかけるのは、
厳しい目で通り向こうの路地裏を凝視しているランパスキャット。
大柄で立派な体躯と隙のない身のこなしは、
彼が幾つもの修羅場をくぐり抜けてきた雄猫であることを物語っている。
「四つか五つくらいの気配を感じる」
御苦労なことだ、とランパスキャットは吐き捨てるように呟いた。
街のリーダーが若いとどうしてもテリトリー破りに遭いやすい。
マンカストラップは強いが優しい。一度目は怒涛の説教で済ますことが多い。
それを良いことに、二度三度と揉め事を起こしにくる馬鹿がいるのだ。
器量の大きいリーダー猫も二度はないと言っている。
一度見かけた面だと判断したら、ランパスキャットは有無を謂わさず相手をとっちめることにしている。
彼だけではない。
街の辺に住むタンブルブルータスやラム・タム・タガーなども同じことをしているらしい。
コリコパットは最近までそれを知らなかったが、
ギルバートまでが街の守り手として身体を張っているとわかれば
年若いことを理由に除け者にされているようで気分が良いはずもなかった。
どうしても手が足りないときだけですよ、とギルバートは言ったが納得できるはずもない。
「そう殺気立つな、気付かれる。散られたら面倒だ」
「ごめん」
目ばかりはぎらついているが、ランパスキャットが纏う空気は静かだった。
大小様々な数知れぬ諍いを経験してきた喧嘩猫にとって、
勢いばかりの余所者など取るに足らない相手に違いない。
だからというわけではないかもしれないが、
ランパスキャットは連れて行ってくれと言ったコリコパットにあっさり同行を許した。
「コリコはここで待て」
「は!?待てってなんだよ、ここまで来て見てろっていうのか?」
「五月蝿いぞ」
声を殺したランパスキャットに睨まれて、コリコパットは次の言葉をぐっと飲み込んだ。
「見せるためになど連れてくるかバカ、作戦てもんがあるだろうが」
「だったら最初から言ってくれよ」
「途中で話を遮っておいてよく言う」
心底呆れたように溜め息を吐いたランパスキャットの横で、コリコパットは身を縮めた。
「合図をしたら来い、手段は問わんから一匹も逃すな」
「了解」
コリコパットの真剣な表情を一瞥して、ランパスキャットは音も立てずに走り出した。
背後に立たれるまで気づかなかったらしい余所者たちが慌てて応戦している。
戦況に目を凝らしていると、不意にランパスキャットが振り返って目が合った。
これだと見極めコリコパットは飛び出した。見ていたばかりの喧嘩に一直線に突っ込んでいく。
「へったくそな戦い方だったな」
「うるせえ!」
掠り傷程度のランパスキャットはニヤリとして傷だらけのコリコパットをからかう。
散々に叩きのめされた余所者たちはつい先ほど這々の体で逃げ帰っていった。
「まあ最初はあんなもんさ。喧嘩なんて場数踏んで学ぶもんで、方法論なんてのは二の次だ」
「ランパス容赦なさすぎ」
「調子に乗せるとまた来るからな。ああいう手合いは取り合わずに実力行使が一番だ」
実際に目の前で見ていたことだけに、コリコパットはふうんと呟くに留まった。
「なんか俺、良いようにおちょくられてた気がする」
「そりゃお前が慣れてないの丸出しだからだろう?挑発にも乗りやすいし」
「うっわ、駄目な見本じゃん」
げっそりとしたコリコパットが傷を舐め始めると、
ランパスキャットはどこから持ってきたのか何かを食べ始めた。
「食うか?初陣祝いだ」
「いい、あんま食欲無いし」
「あれしきで食欲無くすようじゃまだまだだな。ギルバートはもりもり食ってたぞ」
「ギルは食い過ぎなんだ、一緒にするなよ」
さして歳は違わないとコリコパットが認識しているギルバートと比較されて、
しかもまだまだなどと言われては子供っぽいとわかっていながらしょげるしかない。
あからさまに耳が下がった薄褐色の青年を見て、ランパスキャットは小さく笑った。
「まあ今は全体的にギルの方が上だ。あいつは意外に冷静で挑発にも乗らん。
けどな、相手を倒すことばかりに気を取られて守りは下手だ。
力任せだしな。その点コリコはうまく身体を使っていなすことができている」
「いなすことができているって、こんだけ傷だらけなんだけど」
「そりゃあ経験不足だと言っている。俺がコリコを連れてきたのもそこだ。
遅かれ早かれ、俺たちはこの身体一つで誰にも守られない場所に放り出される。
その時に自分がどんな風に動けるのか知っていなけりゃ生きてはいけない」
納得できないからという理由で付いてきてしまったけれど、学ぶべきことは多い。
しょげている場合ではないと、コリコパットはわかっている。
「マンカスあたりは心配性だからお前を連れて行ったりはしないだろうけどな。
あいつは元々諍いを好まないし、だけどいざとなったら冷徹になれる奴だ」
「うん、そうじゃないとリーダーは務まらないってカーバも言ってた」
「そのうち嫌でも何かあったら戦闘要員の頭数に入ってくるだろうが、
今日みたく正面から突っ込むだけじゃ即刻やられるぞ」
「練習するから次は大丈夫だ!」
とにかく相手の攻撃を受け流す。
そして、小柄な体格と俊敏性を活かして反撃する。
パワーに欠けるコリコパットにはこれが理想だ。
これを身につけるにはやはり練習しかない。
単純なコリコパットの目がきらめき始めたのを見て取り、
ランパスキャットは楽しげに口許を歪めた。
「食うか?腹が減ってりゃ戦はできんぞ」
「食べる!」
鳥の肉にむしゃぶりつくコリコパットは飢えた仔猫のようだ。
肉は逃げていった猫たちが残していった戦利品だった。
「今日は無茶をするなよ」
「わかってる」
即答だが本当にわかっているかどうかは不安なところだ。
小さく溜息を吐いたランパスキャットはすぐに苦笑を浮かべた。
「コリコくらい若い奴は無茶してなんぼだけどな」
「うわあ、おっさん発言出た!」
直後、コリコパットの頭上から降ってきた拳骨が盛大な音を立てた。
暫く悶絶していた青年が恨みがましく見上げた先には
薄く笑いを浮かべた喧嘩猫の絶対零度の笑顔があった。
「第二ラウンドいっとくか?」
「いえ・・・無茶はしません」
口は災いの元とはよく言ったものだ。
コリコパットはまた一つ学んだらしい。
ランパスキャットとコリコパット。
ランパスはまだおっさんと言われるのは許せないらしいです。
コリコパットは場数を踏んでもランパスのようにはなれないと思う。
ルール
ルール
起こしておやり、と長老猫に言われてタントミールは部屋の片隅に歩いていった。
すやすやと眠っているのは夜行列車のアイドル、スキンブルシャンクスだ。
既にきっちりと仕事着になっている。今日は彼の乗るノーザンメイル号が走るのだ。
「スキンブル、そろそろ起きないと」
驚かせないようにと加減して声を掛けても、幸せそうに眠る茶虎猫はまるで目を覚まさない。
仕方なく、タントミールは擽るようにわき腹をつついた。
「ふあ…?」
寝ぼけた声と共に目を開けてぼんやりと辺りを見回したスキンブルシャンクスは、
数拍置いてがばりと立ち上がった。
あたふたと服の皺を伸ばすと、取り出した懐中時計をこじ開けるようにして確認する。
「あ、良かった…まだ大丈夫」
ほっとしたように息を吐くと、スキンブルシャンクスはキョトンとしたまま固まっているタントミールに目を向けた。
「起こしてくれてありがとう。吃驚したよね?」
「スキンブルでもそんなに慌てたりするのね」
タントミールがクスッと笑うとスキンブルシャンクスは少しはにかんだ笑みを浮かべた。
「しょっちゅう慌てるよ。もっと余裕があればいいんだけど」
「私から見ればスキンブルはいつも堂々として頼りがいがあるわ。
ギルみたいに真っ直ぐで熱心なのもいいけど、冷静なスキンブルを見ていると素敵だもの」
「ちょっと直球すぎるね、恥ずかしくなるよ」
仲間の前では得意の営業用スマイルも不発で、スキンブルシャンクスは困ったように目を泳がせた。
「時計も読めるのね」
「うん、一応ね。ヒトが持っている時間とかいう概念が僕には必要だから。
列車は僕が大好きな場所だけど、そこにいる限り僕はヒトのルールの中にいる。
遅刻はルール違反になってしまう」
「ふうん。だいたいこれくらいなんて曖昧なのは駄目なのね。
これから駅に行くのでしょう?一緒に行っていい?」
ノーザンメイル号は夜遅くに発車する。今はまだ日が落ちたばかりだ。
ただ、スキンブルシャンクスは夜行列車の乗務員としての仕事がある。
乗客よりも早く着いて準備するのは当たり前なのだ。
「お見送り?ありがとう。タントは割とヒトがいるところも平気だよね」
「元々ヒトと暮らしていたからね」
「そうだったね。じゃあ行こうか」
スキンブルシャンクスとタントミールは微笑んで座っている長老猫に挨拶をして教会を後にした。
「私は列車に乗せてもらったことはないけど、車でよく遠くまで連れていってもらったわ」
街頭が照らす道を並んで歩きながらタントミールが話す。
「私たちの脚ではとても適わないスピードで遠い場所にすいすい行けるなんて、
ヒトはなんて自由なのかしらと思ったわ」
「道のないところに道を敷く、それは鉄道も同じだけどね、
確かにそう考えれば自由にいろんなところにヒトは行けるね。
それで、タントは今でもヒトは自由だと思うかい?」
「どういうこと?今スキンブルだって肯定したじゃない」
「あれ、肯定したっけ?」
スキンブルシャンクスは苦笑してタントミールに目を向けた。
「ヒトはね、そうして自由に旅をするために沢山のルールに縛られているんだよ。
僕も詳しいことは知らないけど、ルールから外れたら今度は捕らわれたりするそうだ」
「ルールって、さっき言っていた遅刻とか?そんなことで捕らわれてしまうの?」
「いや、さすがに時間に遅れただけじゃ捕らわれないと思うけど、列車だったら遅れたヒトは乗れなくなる。
待っていたら他のヒトが身動きできなくなるしさ。
ヒトは自由になるためにルールに縛られることを選んだのかもね」
不思議そうに首を小さく傾げたタントミールは、よくわからないわと言った。
「ルールに縛られるのが好きなのかしら」
「どうかな。ルールがあると楽なんじゃない?何だって判断の基準があれば楽だろう?」
「それもそうね。なんだ、ヒトはそれ程自由じゃないのか」
ほう、と息を吐いてタントミールは空を仰いだ。
「私は野良になって世界が広がった気はしたけど、
ヒトはもっと広い世界を知って自由に飛び回っていると考えていたわ」
「移動手段があるのは確かだよ。空も海も使ってヒトは世界を広げるんだから。
ね、タント。タントは今を自由じゃないと思ってる?」
「いいえ、そんなことはないわ。自由がどういう状態かよくわかんないけど、少なくとも不自由じゃない」
きっぱりと言うタントミールにスキンブルシャンクスは微笑んだ。
「そうさ、僕らは自由じゃないわけじゃないんだ。あはは、わかりづらいなあ。
持っていないものが魅力的に見えるだけでね。僕も言われるよ、猫は自由でいいなあって」
「へえ、ヒトが私たちを羨むことがあるの?」
「彼らにとったら僕ら猫は好きなときに寝られる羨ましい存在さ」
なにそれ、とタントミールは肩を揺らして笑った。
笑ううちに駅が近付いてくる。
「向こうにちょっと見えているのがノーザンメイルだよ。いつかタントにも乗ってほしいなあ」
「是非誘ってちょうだい。行ってらっしゃいスキンブル、気をつけて」
「うん、お見送りありがとう。行ってきます。タントも気をつけて帰ってね」
とびきりの笑顔で敬礼をして、スキンブルシャンクスは駅舎へと走り出した。
どこからか帰ってきたらしい列車がレールを走る音が近付いてくる。
「お土産よろしく」
聞こえるはずはないけれど、タントミールは駅に向かって呟いた。
知らない場所の空気を纏った青い目の青年がここに戻って来たら迎えにこようと思いながら。
ルールに縛られないのが自由というわけじゃないけれど。
タントもスキンブルも、現状には全く不満はないのです。