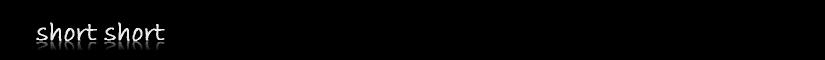耐寒ゲーム
耐寒ゲーム
底冷えのジャンクヤードで、コリコパットはぶるりと身を震わせた。
「寒い」
「冬ですから」
「ギル、つまんない」
口を開けば口から冷気が流れ込む。
空気を吸い込むだけで身体が冷える気がしてならない。
「腹減ったな」
「なかなか食べ物も見つからないですからね」
そう。何も好き好んで外にいるわけじゃない。
腹が減るのだから仕方ない。
寝ていたって腹は減る。
腹が減ったと泣いても喚いても嘆いても、余計に腹が減る。
だからこうして探している。
「場所移すか」
ゴミのてっぺんに立ったランパスキャットが言う。
「どっかいいとこある?」
「心当たりはいくらかなら」
「それじゃあ移動しましょうか。カーバ?」
ギルバートが、ジャンクの間で餌を探しているだろう兄猫を呼ぶ。
「呼んだか?」
「うん。場所移すってさ。あれ?何持ってんだ?」
ひょっこりと顔をのぞかせたカーバケッティの手には、
何やらきらきらと光るものが抱えられている。
「ガラス玉さ。綺麗だろう?」
「キレイっちゃキレイだけど、それじゃあ腹は膨らまないぞ」
コリコパットは呆れたように白い溜め息を吐いた。
「お前も酔狂な奴だな。このクソ寒いのにそれを見つけてどうなるんだ?」
「お前たちが無粋なんだろう?この美しさに心が洗われないのか」
音も立てずに地面まで降りたランパスキャットは、
ギルバートとコリコパットに向けてひょいと片眉を持ち上げて見せる。
また病気が始まった、と言わんばかりだ。
「お腹が空いてるんですよ。頭に糖分が回ってないんです、きっと」
「なんか厭な予感するな。早く次に行きたいのに」
冬の日差しにきらきらと光るガラス玉を抱えて近づいてくる褐色ぶちの猫を、
ギルバートとコリコパットは遠くを見るような眼差しで眺めている。
「なあ、ランパス」
カーバケッティは、ぽむとランパスキャットの肩を叩いた。
白黒の男は厭そうに眉を寄せる。
「お前の瞳はこのガラス玉のように美しく透き通っている」
「・・・てめえ」
かろうじて爪をむき出しにするのを堪えたランパスキャットは、
肩に掛った男の手を邪険に払いのけて冷笑を浮かべた。
「そろそろ貴様の彼女への口説き文句を俺で試すのは止めたらどうだ」
「そうもいかなくってね」
ふるりと緩く首を振って、カーバケッティはギルバートに目を向けた。
「何です?」
「ギル。お前が修練で流す汗はこのガラス玉のように煌めいている」
身構えていた筈のギルバートがよろめくように一歩後ずさった。
「俺、さっきより寒くなったんだけど」
「コリコ、僕もですよ」
「しかも俺の方向いてるし!」
何とも胡散臭い笑顔を浮かべた紳士はコリコパットに視線を定めた。
「お、俺には何も言うな!」
「その熱さはこのガラス玉を溶かしてしまいそうだ」
「うっわ、予想以上のダメージかも」
青褪めたコリコパットはふらついてジャンクに躓き派手に転んだ。
「泣きっ面に蜂ってやつですね」
「腹減った上にこれだと思うと・・・今日はついてないとしか言えない」
「そう言ってやるなコリコ」
ランパスキャットが小さく嗤ってカーバケッティの首根っこを掴んだ。
「こいつも空腹なんだ。仕方ねえからとびきりの餌場を教えてやる。
来い。この寒空にこんな寒風に晒されているのはたまらん」
「酷い言い草だなランパス。せっかく褒めてるのに」
「そんな労力があるなら食い物を探せ」
歩き出したランパスキャットに引きづられるようにカーバケッティも歩き出す。
ギルバートは肩を竦めると、コリコパットを引っ張り上げるように立たせた。
「行きましょう」
「おう。寒いからな」
「そうですね、冬ですから。もっとも、それだけじゃないようですが」
顔を見合わせて苦笑いを浮かべたギルバートとコリコパットは
先を行く兄猫たちを追って歩き始めた。
テーマは「ガラス玉」
寒さと空腹で紳士が現実逃避を試みているようです。
ぱらぱらいたた
ぱらぱらいたた
空から氷の粒が降り注いでいる。
屋根に、石畳に、裸の木や塀に、ぶつかっては小さな音を立てる。
「こうして霰が降るとぱらぱらって表現するけど」
すっかりくたびれた毛布にくるまったディミータがふと呟く。
「色んなものに当たる音なのよね」
「そうね。まさか霰そのものがぱらぱらって音はたてないでしょうし」
そうなったら不気味なことこの上ない。
「厭だわ、想像しちゃった。霰がぱらぱらって鳴りながら落ちてくるの」
「ディミって想像力豊かなのね」
「今のを想像力豊かだって言うの?」
ボンバルリーナは答えずに妖艶に笑みを深める。
「リーナも何か想像してみなさいよ。座ってるだけじゃ寒いし」
「あら。考え事をしてみても寒いのは寒いわ」
「そうだけど」
不満そうなディミータの毛並みを整えてやりながら、そうねえとボンバルリーナは呟いた。
「あの霰が、ぱらぱらって歌いながら空からやってくるというのはどう?」
「おもしろいわね。楽しそうでいいわ」
雲に覆われた空から、雲の子どもの霰たちが地上に降りてくる。
ぱらぱらと歌いながら、遠足気分でやってくる。
「私なんかよりリーナの方がよっぽど楽しいこと考えるじゃない」
「そう?」
「そうよ。ねえ、寒いんだから入ったら?」
「ありがとう、そうさせてもらうわ」
持ち上げられた毛布の端から身を滑り込ませたボンバルリーナは、
冷えた身体をディミータの横に落ち着けた。
「随分冷えてるじゃない」
「これくらいなら平気よ。でも、確かに今日は寒いわね」
「霰が降るくらいだしね。これじゃあ太陽は期待できないわ」
美しいメス猫が並んで霰の奏でるパーカッションに耳を傾ける。
彼女らには、パーカッションではなくて霰の歌声に聞こえているのかもしれない。
「ねえ、ディミ」
「なあに?」
「ぱらぱらって歌いながら霰が空から降ってくるでしょう?」
ボンバルリーナは楽しそうに目を細めた。
「それでね、道に衝突して"いたっ"て言うの。
"いたっ""いたっ""いたっ"てね。そう聞こえない?」
「・・・そうかしら」
耳とは不思議なもので、そう言われればそう聞こえてしまう。
大きくため息をついたディミータは、もぞもぞと毛布に潜り込んだ。
「リーナって」
「私が何か?」
「想像力豊かだけど、シュールよね」
毛布の中から届くくぐもった声に、ボンバルリーナはくすくすと笑った。
「ええ、そうね。よく言われるわ。主に貴女にね」
うっとりするような微笑みを浮かべてシュールなことを言うボンバルリーナ。
まっすぐなディミータはいつまでも敵わない相手。
意地っ張りにキスを
意地っ張りにキスを
行くから、というタントミールを思いとどまらせて正解だった。
ギルバートはそんなことを考えながら冷たい石の上を軽く駆けていた。
寒さに弱い彼女のことを慮って、待ち合わせの場所は彼女の塒からほど近い教会にしてある。
「えっと・・・ここ、か」
住宅街の十字路で束の間立ち止まったギルバートは、
教会へと続く道からそれていつもは使わない細い道へと脚を向けた。
タントミールとの約束は午後からで、まだ時間がある。
目的の場所を通り過ぎてしまわないように緩く駆ける。
「急に暖かくなったり寒くなったりするから風邪引いたんでしょうね」
少し駆けたくらいでは息が上がることもないのか、ギルバートは走りながら平然と呟いた。
自他共に認める体力バカのギルバートはこのところ風邪などというものには無縁だである。
風邪を引いたのは彼でなく、彼の兄貴分ともいえるカーバケッティのことだ。
向こう見ずなところのあるギルバートが突っ走るのをさりげなく止めてくれる自称紳士のぶち猫は、
さすがに生まれたときから野良猫だから少々のことでくたばったりはしない。
だが、昨夜から妙に静かなのが気になってギルバートが兄猫を訪ねると、
カーバケッティはぐでりと毛布に伸びたままで、いつもの大きくて丸い目が半分くらい閉じられていた。
ちなみに、カーバケッティの寝床はギルバートの塒の目と鼻の先にある。
というよりも、ギルバートの塒がカーバケッティのテリトリーの一部と言ってもよかった。
年若いギルバートでは、自分だけのテリトリーを切り取っていくだけの力はまだ十分と言い難い。
この先ずっと兄猫のテリトリーを甘んじて使わせてもらうつもりは毛頭無いが、
カーバケッティはギルバートを追い出すつもりはまるで無いらしい。
「大丈夫とは言っていたものの・・・っと」
向こうの方で自転車のブレーキ音が聞こえる。
それほど人間たちの行き来があるところではないようだが、
念のためギルバートは塀によじ登ってそのままその上を歩くことにした。
「もう少し先のようですね」
目を眇めて明るい道の向こうを見やると、ギルバートは軽やかに石塀の上を走り始めた。
兄猫の言葉を早く相手に伝えなければならないとギルバートは思っている。
近くに暮らしているとは言え、日頃は全くと言って良いほど互いに干渉はしない。
でも、ギルバートが怪我をすれば異変を感じるのかカーバケッティはやってくるし、
昨夜のようにギルバートから訪ねることも無いわけではない。
とろんとした目のカーバケッティは、第一声には「うつされたくなければ帰れ」と言って、
何かできないかと訊ねたギルバートにかなりそっけない態度を取っていた。
「案外強情なんですよね」
石塀がいったん途切れて2フィートほど離れているところから再び向こうに続いていたが、
その間をひらりと難なく飛び越え着地しながらギルバートは溜め息を吐いた。
無論、そういう部分も充分に心得ているわけで、ギルバートは今朝再び兄猫のところを訪れた。
相変わらず毛布に埋まったまま顔を上げるのも億劫そうなカーバケッティは、
二度目の何かできないかというギルバートの問いに渋々といった体で言づてを頼んだのだ。
「こっち、だったかな」
朧気ながらも記憶は確かだったようで、細い路地に入ったギルバートの鋭い目は目的地を捉えた。
広い緑地公園の片隅にある廃材置き場の近く。
うち捨てられたような人工物も、長い年月で苔が生え草に埋もれてしまえば立派な家だ。
陽光降り注ぐ塒の入り口にしっかと立って、ギルバートはことづての相手を呼ばわる。
「おはようございます!ディミ、いますか?」
陽の光は暖かいとはいえ風は冷たい。
走ってきて温まった身体が冷えないうちに出てきて欲しいとギルバートが思った矢先、
茶色く乾いた草の間にある入り口から音も立てずに家主が出てきた。
「おはようギルバート。珍しいわね」
「お、おはようございますボンバル。ここ、ディミの塒では?」
「細かいことはいいのよ。ディミはすぐに出てくるけど、急ぐなら入っていいわよ」
「いえ、さすがにそれは」
ここがジェニエニドッツの塒なら遠慮せずに入るのだが、
ディミータとボンバルリーナが寝床にしているらしい場所に立ち入るのはギルバートでなくても気が引ける。
ギルバートが苦笑を浮かべて入るのを遠慮していると、すぐに橙色の雌猫が出てきた。
「おはようギル。私を呼んだ?」
「呼びました。おはようございます。カーバから伝言です」
「カーバ?」
ディミータの目つきがいやに鋭くなったなと思いつつ、ギルバートは頷いた。
「せっかくだけど風邪を引いてしまったから来ないでくれ、だそうです」
「風邪?」
「はい。どうもかなり具合が悪そうで。昨日の夜から毛布に貼り付いているようです。
僕にできることは何も無いそうで・・・こうして伝言を預かってくるのが精一杯でした」
申し訳なさそうにするギルバートをボンバルリーナは不思議そうに見やり、
次いでディミータに向けて小さく首を傾げた。
「ディミ、今日カーバと約束していたの?約束なんて無いって言っていたのに」
「してないわよ。ほんとに、あのバカ。意地張ってないでギルに看病頼めばいいのに」
「そんなカーバなんて想像できませんが」
ギルバートが呟くと、小さい頃からカーバケッティを知っているボンバルリーナも同意するように頷いた。
「私だってあいつが強情でプライド高くって周りに迷惑掛けたがらないことくらい知ってるわよ。
・・・ほんとバカ。苛々するしバカだし!でも放っておくわけに行かないでしょ!」
「ええ、そうね。行くの?」
「行く」
にこやかに問いかけたボンバルリーナに低い声で一言だけ答えると、
ディミータは素晴らしい早さでギルバートがやって来た方向へ向かって走り出した。
「素晴らしいダッシュですね」
「バカバカ言っても凄く心配なのよ。カーバだって、ディミが来たら邪険にはできないでしょうし」
「そうですね。僕には弱ってるところを見せたくないはずです、ディミが行ってくれて良かった」
ギルバートが安堵の表情を浮かべる。
すぐにディミータの姿は見えなくなり、ボンバルリーナもくすっと笑った。
「ギルもありがとう、タントとデートの前にここまで来てくれて」
「何でご存知なのです?」
「昨日タントと会った時に聞いたのよ。タント、すっごく楽しみにしていたわ。
ディミはちゃんとカーバのところに行くから大丈夫。私も出掛けるわ」
そう言われて初めて、ギルバートはボンバルリーナの毛並みが綺麗に整っていることに気付いた。
それはいつものことなのだけれど、塒にいるだけの時にここまで丹念に毛繕いする必要も無い。
そして、今日という日のことを考えれば彼女の行き先も見当がつく。
「ボンバルは」
「何?」
「どういったものをランパスに渡すのです?ただの興味なのですが」
タントミールはいつも美味しい物を用意してくれる。
色気より食い気のギルバートをいつだって喜ばせてくれる。
そんなだから、ギルバートには喧嘩猫は一体何を貰っているのだろうかとただ疑問に思うのだ。
「特に何も用意してないわよ。まあ、敢えて言うなら私自身かしら」
「なるほど。"プレゼントは私"を地で行くわけですね」
「そういうことかしら。それほどキラキラしたシチュエーションにはならないでしょうけど」
コロコロと笑うと、ボンバルリーナは上機嫌で出掛けていった。
自分の彼女がタントミールで良かったと心の底から思いながらギルバートも来た道を引き返す。
行きに辿ってきた石塀によじ登り、その日だまりの中で丁寧に毛繕いをしてから
タントミールと待ち合わせをしている教会へと足取り軽く駆けてゆく。
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
「カーバ!」
寝床とは勝手に飛び込んでいいような場所ではない。
だが、今はそんなことはどうでもいいのだ。
ディミータは走ってきた勢いそのままで褐色ぶち猫の塒に突入すると、
無駄に広いスペースの片隅で毛布にくるまっている雄猫に歩み寄った。
「ディミ、来ないでくれと言っておいたのに」
「煩いわよこのバカ。いつからあんたは捻くれ者になったのよ。
来てくれって伝言してくれたってちゃんと来たわ」
カーバケッティの傍で、ディミータはそう囁いて微笑んだ。
「風邪引いたから来てくれなんて言えないじゃないか」
「意地っ張りね」
「なけなしのプライドだ。本当はけっこうきつかったんだ。
ギルに言えばあいつは真面目だから面倒も見てくれただろうさ。
でも、今日ばかりはあまり心配させたくないし。ギルは今日を楽しみにしてただろうから」
そこまで言うと、カーバケッティは疲れたように目を閉じた。
「気を遣うのも程ほどにしなさいよ」
「ディミなら来てくれると思っていた」
「そうよ、見事に乗せられたわ。ほら、もういいから寝ておきなさい。
何か食べるもの調達してきたら今日はずっとここにいるから」
「そりゃ最高だ。それじゃあ少し眠らせて貰おう」
微かに笑みを浮かべたまま、カーバケッティは規則的な寝息を立て始めた。
ディミータは少し乱れている毛布を整えてから食べ物を探しに外に出ようとし、
ほんの少し躊躇ってから引き返して眠っているぶち猫の顔を覗き込んだ。
「何も用意してないから、これだけね」
そう言って、ディミータはカーバケッティの少し熱い額に軽くキスをした。
「可愛い弟分のデートを気遣う前に自分のこと気遣いなさいよ」
そんなことを呟きながら、ディミータは光の中を歩き出した。
まずはジェニエニドッツのところに行って、おいしいものをねだってみようかと思いながら。
ディミータという名のツンデレの具現化。本当はそんなんじゃないと思うのに。
案外自分はカーバに甘いな。いつも変な奴扱いしてるからたまに可哀想になるんです。
別に、舞台で見てるカーバは変だとは思わないのですが。。。
ムーンライト・メヌエット * new *
ムーンライト・メヌエット
路地裏の薄汚れたごみ箱から握りつぶされたらしき紙が零れ落ちた。
カサリと僅かな軽い音を立てたそれは、折からの風に煽られて石畳を滑ってゆく。
冷たい風は細い悲鳴のような音を立て、紙屑を枯葉と共に街の片隅に吹き寄せる。
緩急を付け、時に小さく渦を巻きながら、寒風は街を過ぎる。
「感心しないな、この寒空の下で月見など」
からからに乾いた吹きだまりを踏みつけて、大柄な雄猫は溜め息を吐いた。
夜の街に降り注ぐ明るい月明かりの下、
白と黒の毛並みは青白い光に縁取られるように浮かび上がる。
「目の錯覚かしら?あなたを少しでも美しいと思ってしまうなんて」
「寝言は塒に帰ってからにした方がいいぞ、ボンバルリーナ」
暖かみのない言い草はランパスキャットの常であり、
それを十分に知っていて慣れているボンバルリーナは気を悪くするどころか笑みを深めた。
「寝ていないもの、寝言ではないわ」
「だった言い直そう。冗談はほどほどにしろ。凍える前に早く帰れ」
「厭よ」
実にあっさりと言い放ったボンバルリーナは、するりとランパスキャットに身体を寄せた。
どこで何をしてきたのか、逞しい白黒の身体は外気温に反して温かい。
「血の臭いがするわ」
ランパスキャットは妖艶な雌猫を押しやろうとして、その身体があまりに冷たいことに気付き、
眉を顰めながら逆に胸元に抱き寄せた。
「俺の血じゃない」
「知っているわ、それくらい」
暖かさにほっとしたようにボンバルリーナは吐息を零し、
彼女の代わりに風を受けている雄猫を見上げた。
強く吹き付ける風に耳揺らしながら、明るい月の光を少し長めの毛並みで受け止めている。
冷たい風に晒されてさえ彼の表情は少しも変わらない。
「あなたはいつだって強いもの」
「俺が今の立ち位置にいるための絶対条件だからな。街を守れるだけの力が無くては」
「ねえ、ランパス」
ボンバルリーナは艶やかな声で雄猫の言葉を遮った。
「せっかく私がここにいるのよ、街ではなく私を守ると言って欲しいわ。
その方がぐっと来るでしょう?」
「・・・そうか?」
怪訝そうな表情でボンバルリーナを見下ろしたランパスキャットは、
彼女の美しくも妖しい笑みを前に言葉を詰まらせ、
だがすぐに口の端に笑みを浮かべて顔を近づける。
そのままこつりと額をぶつけると、彼はボンバルリーナの耳元で囁いた。
「踊ろう」
低い声が彼女の耳を震わせる。
言葉を吹き込まれた場所から脚の先まで血が駆け巡るような気さえして、
ボンバルリーナは寒さを忘れてランパスキャットから僅かな距離を取った。
踊るのに一番良い距離を。
「ぐっと来たわ」
「それは何より」
月明かりは眩しいライト。
風は旋律。短調気味なのはご愛敬。
青く冷たい月光のステージに立つ二匹の猫の傍、渦巻く風が枯葉を散らしてゆく。
心の臓に似た葉が巻き上げられた刹那、二匹の猫は月に輝きながら舞い始めた。
寒風吹きすさぶ路地裏なんて淋しいのは当たり前ですね。
ボンバルリーナだって甘えるし、ランパスキャットだって甘えさせるのです。
踊ればちょっとは暖まるのかな。